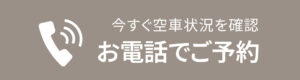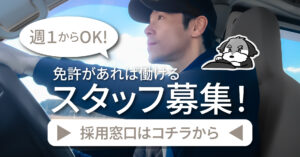愛犬が吠えるのをやめさせる方法がわからず、「ご近所に迷惑をかけていないか」「どうして吠えるの?」と悩んでいませんか。その吠えには、必ず理由があります。
この記事では、犬が吠える5つの気持ちを解き明かし、やってはいけないNG対応、そしてドッグトレーナーが実践する状況別の正しいしつけ方法まで、具体的かつ分かりやすく解説します。
この記事を読めば、愛犬の気持ちを理解し、吠えに効果的に対処するための知識が身につき、穏やかで楽しい毎日を取り戻す第一歩を踏み出せます。
まずは結論!犬が吠えるのをやめさせるための状況別クイックガイド

犬の吠えに悩んだ時、まず試してほしい基本的な対処法を状況別にまとめました。それぞれの吠えには異なる原因が隠れており、その原因に合ったアプローチをすることが解決への一番の近道です。以下の表で、あなたの愛犬がどのケースに当てはまるかを確認し、最初のステップとして試してみてください。
これから紹介する対処法は、あくまで応急処置的なものです。本質的な解決のためには、なぜその行動を取るのかという愛犬の気持ちを理解することが不可欠です。詳しい原因の解説や、より効果的なトレーニング方法は、この後の見出しでじっくりと解説していきますので、ぜひ最後まで読み進めてみてください。
| 状況 | 主な原因 | クイック対処法 |
|---|---|---|
| インターホン・来客 | 警戒・縄張り意識 | 「ハウス」などの指示で落ち着ける場所へ誘導する |
| 散歩中の他の犬・人 | 恐怖・社会化不足 | 相手との距離を取り、吠えずにいられたら褒める |
| ごはん・散歩の催促 | 要求・学習 | 吠えている間は徹底的に無視し、静かになったら応える |
| 留守番中 | 分離不安・退屈 | 出かける前に知育おもちゃなどを与えておく |
なぜ吠えるの?犬が飼い主に伝えたい5つの気持ち

犬の「吠え」は、人間にとっての「言葉」と同じ、大切なコミュニケーション手段の一つです。ただうるさいと捉えるのではなく、その声で何を伝えようとしているのかを理解しようとすることが、問題解決の第一歩となります。ここでは、犬が吠える主な理由を5つの気持ちに分類して解説します。愛犬の行動と照らし合わせながら、その心を探っていきましょう。
①警戒・恐怖:「知らない人や音が怖い!」縄張りを守るための警戒吠え
警戒吠えは、自分の縄張りを守ろうとする犬の本能からくる行動です。インターホンの音や見知らぬ来客、窓の外を通りかかる人や車など、自分のテリトリーに近づく未知の対象を「侵入者」と判断し、威嚇したり群れの仲間である飼い主に危険を知らせたりするために吠えます。
この吠えは、番犬としての気質が強い犬種によく見られますが、臆病な性格の犬が恐怖心から吠えてしまうケースも少なくありません。犬にとっては、自分の家や家族を守るための重要な仕事のつもりなのです。ただ叱るのではなく、その対象が怖くないものであることを教え、安心させてあげることが解決への鍵となります。
②要求・催促:「ごはんちょうだい!遊んで!」飼い主の気を引きたい要求吠え
要求吠えは、「吠えたら要求が通った」という過去の成功体験から学習した行動です。例えば、ごはんの準備中に足元で吠えたら、早くごはんをもらえた。ケージの中で吠え続けたら、根負けした飼い主が出してくれた。犬はこうした経験をしっかりと記憶し、「吠える=願いが叶う」という公式を学びます。
一度この学習が成立してしまうと、犬は要求を通したい時に吠えるようになります。「お散歩まだ?」「おもちゃを投げて!」といった催促の気持ちを、吠えるという手段で表現しているのです。このタイプの吠えをなくすには、吠えても無駄であることを根気強く教える必要があります。
③興奮・喜び:「嬉しい!楽しい!」感情の高ぶりによる興奮吠え
興奮吠えは、飼い主さんの帰宅時や大好きな遊びの最中など、ポジティブな感情の高ぶりを抑えきれずに声として発散している状態です。決して悪い意味合いで吠えているわけではなく、人間が歓声をあげるのと同じようなものだと考えられます。そのため、無理にやめさせる必要がない場合も多いです。
しかし、興奮がエスカレートしすぎてコントロールが効なくなったり、吠え声がご近所の迷惑になったりする場合は対処が必要です。特にドッグランなどで他の犬とのトラブルに発展する危険性もあるため、興奮状態の犬を落ち着かせる「クールダウン」の練習をしておくと、いざという時に役立ちます。
④ストレス・不安:「退屈だよ」「ひとりは寂しい…」分離不安や運動不足によるストレス吠え
ストレス吠えは、運動不足、長時間の留守番、コミュニケーション不足など、心身の欲求が満たされないことへの不満が原因です。有り余ったエネルギーや退屈さ、孤独感といった負の感情が、吠えるという行動につながります。自分の尻尾をぐるぐる追いかけたり、手足を執拗に舐め続けたりといった他の問題行動と併発することも少なくありません。
特に、飼い主と離れることに極度の不安を感じる「分離不安」が原因の場合、飼い主の外出中ずっと吠え続けることもあります。分離不安とは、単なる寂しがりとは異なり、精神的な問題が背景にある状態です。この場合は、生活環境の見直しや遊びの工夫に加え、専門家への相談も視野に入れる必要があります。
⑤習性・本能:「仲間を呼ぶぞー!」遠吠えなどの習性による吠え
遠吠えは、遠くにいる仲間とコミュニケーションを取っていた、犬の祖先であるオオカミ時代からの名残です。救急車や消防車のサイレンの音、他の犬の遠吠えなどが聞こえると、それに呼応するように「ワオーン」と特徴的な声で鳴くことがあります。これは犬にとって非常に本能的な行動であり、完全にやめさせることは困難です。
この行動自体に大きな問題はありませんが、頻繁に起こる場合や夜中に鳴き続ける場合は対処が必要です。遠吠えが始まったら、おやつやおもちゃで気を引いたり、「おすわり」などの簡単な指示を出したりして、意識をこちらに戻してあげると中断させやすいです。
やってはいけない!逆効果になる3つのNG対応

愛犬の吠えを今すぐ止めさせたい一心で、ついやってしまいがちな行動が、実は問題をさらに悪化させているかもしれません。犬のしつけにおいては、良かれと思った行動が裏目に出ることがよくあります。ここでは、多くの飼い主さんが陥りやすい、吠えに対するNG対応を3つご紹介します。ご自身の対応を振り返ってみましょう。
①大声で叱る:犬は「応援してくれている」と勘違いする
犬が吠えている最中に飼い主が「うるさい!」「静かに!」と大声で叱ることは、火に油を注ぐ行為です。人間の感覚では「叱っている」つもりでも、興奮している犬には「飼い主も一緒に大きな声で騒いでくれている!」「もっと頑張れと応援してくれている!」としか伝わりません。
その結果、犬はさらに興奮し、声も大きくなってしまいます。犬に静かにしてほしい時は、感情的に怒鳴るのではなく、落ち着いた低いトーンの声で「ハウス」「おすわり」など、短く具体的な指示を出す方が効果的です。飼い主が冷静な態度を示すことが、犬を落ち着かせるための第一歩です。
②叩くなどの体罰:恐怖心から問題行動が悪化する可能性がある
マズル(鼻先)を掴んだり、お尻を叩いたりといった体罰は、絶対にやめてください。このような罰は、犬に痛みと恐怖を与えるだけで、なぜ吠えてはいけないのかを理解させることには繋がりません。むしろ、「飼い主は自分に危害を加える怖い存在だ」と認識させ、築き上げてきた信頼関係を根底から覆してしまいます。
恐怖によって一時的に吠えるのをやめたとしても、それは根本的な解決にはなりません。飼い主の手を怖がるようになったり、恐怖心から自己防衛のために噛みつくようになったりと、別の深刻な問題行動を引き起こす原因にさえなり得ます。犬のしつけは、罰ではなく、信頼関係に基づいて行うことが大原則です。
③おやつなどで気を引く:「吠えれば良いことがある」と誤学習させてしまう
吠えている犬を黙らせるために、その場しのぎでおやつをあげるのは最も避けたい対応の一つです。この行動は、犬に「吠えるとおやつがもらえる」という間違った学習をさせてしまいます。犬は「吠える」という行動と「おやつ」というご褒美を直接結びつけ、要求を通すための手段として吠えを多用するようになります。
これは「要求吠え」を意図的に強化してしまう行為に他なりません。おやつは、あくまで「吠えるのをやめて静かにした瞬間」や「飼い主の指示に従えた瞬間」にご褒美として与えるべきものです。タイミングを間違えると、ご褒美が問題行動を助長する原因になってしまうことを覚えておきましょう。
【状況別】今日からできる!犬の吠えをやめさせる具体的トレーニング法

ここからは、犬の吠えをやめさせるための具体的なトレーニング方法を、よくある状況別にご紹介します。吠えの原因が違えば、効果的なアプローチも異なります。愛犬の行動をよく観察し、どのケースに最も当てはまるかを見極めてから、根気強くトレーニングに取り組んでみましょう。大切なのは、一貫した態度で続けることです。
ケース1:インターホンや来客に吠える場合
インターホンや来客に対する吠えは、警戒心や縄張り意識が主な原因です。このトレーニングのゴールは、「インターホンの音や知らない人は怖くない、むしろ良いことが起こる合図だ」と犬に学習させることです。恐怖心を楽しい気持ちに上書きしてあげましょう。
ステップ1:インターホンの音に慣れさせる(音慣れ)
まずは、インターホンの音に対するマイナスイメージを払拭します。家族に協力してもらい、インターホンを鳴らしてもらいます。音が鳴った瞬間に、すかさず特別なおやつをあげましょう。この時、犬が吠える前に与えるのがポイントです。最初は音量を小さくしたり、録音した音を使ったりして、犬が吠えずにいられるレベルから始め、「音=おやつの合図」という関連付けを何度も繰り返します。
ステップ2:「ハウス」の指示で落ち着ける場所へ誘導する
音が鳴ったら興奮して玄関に走って行くのではなく、自分の居場所で落ち着けるように教えます。日頃からクレートやベッドを「ハウス」と呼び、そこでリラックスする練習をしておきましょう。インターホンの音慣れと並行し、音が鳴ったら「ハウス」と指示し、落ち着いてハウスに入れたらたくさん褒めてご褒美をあげます。これにより、興奮する代わりに落ち着くという行動を習慣化させます。
ステップ3:来客からおやつをもらい「来客=良いことがある」と学習させる
最終ステップとして、「来客は自分に良いことをしてくれる存在だ」と教えていきます。協力してくれる友人などに協力してもらい、来客を装って家に入ってきてもらいます。犬が落ち着いていられたら、その人から直接おやつをあげてもらいましょう。これを繰り返すことで、「知らない人=怖い」というイメージが、「知らない人=おやつをくれる嬉しい存在」へと変化していきます。
ケース2:散歩中に他の犬や人に吠える場合
散歩中にすれ違う相手に吠えてしまうのは、恐怖心や社会化不足が大きな原因です。無理に近づけて慣れさせようとするのは逆効果。このトレーニングのゴールは、「他の犬や人がいても、飼い主さんに注目していれば大丈夫」という安心感と信頼関係を育むことです。
ステップ1:相手と距離を取り、吠えずにいられたら褒める
犬が相手を認識しても、まだ吠え出さない距離を保つことが最も重要です。その距離まで近づいたら立ち止まり、犬が相手を見ても吠えずにいられた瞬間に「いい子!」と褒めておやつをあげます。もし吠えてしまったら、それは距離が近すぎるサインです。すぐにその場を離れ、もっと遠い距離からやり直しましょう。犬に成功体験を積ませることが大切です。
ステップ2:おやつやおもちゃで注意を飼い主に向ける
すれ違う対象ではなく、飼い主に意識を向けさせる練習です。他の犬や人が遠くに見えたら、名前を呼んだり、おやつを見せたりして、犬の注意をこちらに引きつけます。アイコンタクトが取れたり、飼い主の方を向いたりしたら、すかさず褒めてご褒美をあげましょう。これにより、「怖いもの」から意識をそらし、飼い主と一緒にいれば安心だと学習していきます。
ステップ3:すれ違う練習を繰り返し、少しずつ距離を縮める
ステップ1と2ができるようになったら、少しずつ相手との距離を縮めていきます。焦りは禁物です。犬がリラックスできているか、表情や仕草をよく観察しながら行いましょう。もし途中で吠えてしまっても叱らずに、また吠えずにいられる距離まで戻って練習を再開します。この地道な繰り返しが、犬の自信に繋がっていきます。
ケース3:ごはんや散歩の前に要求して吠える場合
ごはんの準備中や散歩に行く時間になると吠えて催促する。これは、「吠えれば要求が通る」と犬が学習してしまった結果です。このトレーニングのゴールは、「静かに待っていた方が、結果的に要求が早く通る」ということを犬に再学習させることです。飼い主の一貫した態度が試されます。
ステップ1:徹底的に無視を貫く
犬が要求して吠えている間は、視線も合わせず、声もかけず、完全に無視をします。ここで「うるさい!」と反応したり、チラッと見てしまったりするのはNGです。犬にとってはどんな反応でも「構ってもらえた」というご褒美になってしまい、吠えを強化してしまいます。準備の手をいったん止め、背中を向けてその場を離れるくらい徹底しましょう。
ステップ2:吠えるのをやめて、静かになった瞬間に要求に応える
犬が吠えるのを諦めて、一瞬でも静かになったタイミングを見逃さないでください。その瞬間に「いい子」と褒め、すぐに準備を再開し、ごはんをあげたり散歩に連れて行ったりします。これを繰り返すことで、犬は「吠えている間は、良いことは何も起こらない」「静かにすれば、ごはんや散歩が手に入る」という新しいルールを学んでいきます。根比べになりますが、家族全員でルールを統一して臨むことが成功の鍵です。
ケース4:留守番中やケージの中で吠える場合
飼い主の不在時やケージに入っている時に吠え続けるのは、分離不安や退屈、ケージへの悪いイメージが原因と考えられます。このトレーニングのゴールは、「ケージやハウスは世界一安全で落ち着ける場所だ」と犬に認識させ、ひとりの時間もリラックスして過ごせるようにすることです。
ステップ1:ケージやハウスが安心できる場所だと教える(クレートトレーニング)
ケージを罰を与える場所ではなく、犬だけの特別なパーソナルスペースにしてあげましょう。まずは扉を開けたままにし、中におやつやお気に入りのおもちゃを置いて、犬が自発的に入るのを待ちます。中で食事をさせたり、特別なご褒美をあげたりするのも効果的です。こうしたポジティブな経験を積み重ね、「ケージ=良いことがある場所」というイメージを作っていきます。
ステップ2:留守番前に運動させてエネルギーを発散させる
犬を留守番させる前には、長めの散歩やボール遊びなどで十分に体を動かさせましょう。体力が有り余っていると、退屈さから吠えやすくなります。適度な疲労感は、犬をリラックスさせ、留守番中に落ち着いて眠りやすくなる効果があります。心身ともに満たされた状態でお留守番をスタートさせてあげることが大切です。
ステップ3:知育おもちゃなどを活用し、退屈させない工夫をする
犬がひとりで過ごす時間に、夢中になれるアイテムを用意してあげましょう。中におやつを詰めて、時間をかけて取り出して遊ぶタイプの知育おもちゃは、犬の退屈しのぎに最適です。飼い主が出かける直前に与えることで、犬の意識が「飼い主がいなくなる寂しさ」から「おもちゃで遊ぶ楽しさ」へと切り替わり、スムーズな外出に繋がります。
それでも吠えが治らない時に試したい対策と相談先

これまで紹介したトレーニングを試しても、なかなか愛犬の吠えが改善しない。そんな時は、少し視点を変えたアプローチが必要かもしれません。また、一人で抱え込まずに専門家の力を借りることも、愛犬と飼い主さん双方にとって、より良い結果に繋がることがあります。ここでは、次の一手として考えられる対策と相談先をご紹介します。
運動量を増やしてストレスを発散させる
日々の運動が足りているか、もう一度見直してみましょう。特にエネルギーレベルの高い犬種の場合、飼い主が思っている以上に多くの運動量を必要とします。有り余ったエネルギーが吠えという形で発散されている可能性は十分に考えられます。いつもの散歩の時間を10分延ばす、コースに坂道を取り入れる、週末はドッグランで思い切り走らせるなど、運動の質と量を向上させる工夫をしてみてください。心身が満たされれば、問題行動が自然と減少することもあります。
室内環境を見直す(外が見えないようにする等)
吠えのきっかけとなる「刺激」を、物理的に取り除いてあげることも非常に有効な手段です。特に警戒吠えの場合、窓の外の通行人や車の動きが引き金になっていることがよくあります。窓の下半分に目隠しシートを貼ったり、カーテンを閉めたりして、外の様子が見えないようにするだけで、犬が反応する機会は劇的に減ります。また、犬が落ち着いて過ごすケージやベッドを、窓や玄関から離れた静かな場所に移動させてあげるのも良い方法です。
プロのドッグトレーナーや行動診療科の獣医師に相談する
様々な対策を講じても改善が見られない場合は、迷わず専門家に相談しましょう。家庭犬のしつけを専門とするドッグトレーナーは、実際に犬の様子や飼い主との関係性を見て、その家庭に合った具体的なトレーニングプランを提案してくれます。また、吠えの原因が分離不安や常同障害など、より深刻な心の問題や病気が疑われる場合は、獣医行動学の専門知識を持つ「行動診療科」の獣医師への相談が適切です。一人で悩まず、専門家の客観的な視点を取り入れることが、解決への一番の近道となるはずです。
犬の無駄吠えに関するよくある質問
ここでは、犬の吠えに関して飼い主さんからよく寄せられる質問にお答えします。多くの人が抱く疑問を解消することで、愛犬への理解をさらに深める手助けになれば幸いです。
Q1. 吠えやすい犬種はありますか?
はい、犬種が持つ歴史や役割によって、吠えやすい傾向を持つ犬種は存在します。例えば、チワワやポメラニアン、ヨークシャー・テリアなどの小型犬は、番犬として侵入者を知らせる役割を担ってきたため、警戒心が強く吠えやすい傾向があります。また、ビーグルやダックスフンドなどの猟犬は、獲物を見つけたことを声で知らせる習性があるため、鳴き声が大きく響きやすいです。ただし、これはあくまで一般的な傾向であり、個々の性格や育った環境による影響の方が大きいことを理解しておく必要があります。
Q2. 子犬のうちからできる吠えの予防策はありますか?
子犬期における「社会化」が、将来の吠えを予防する上で最も重要です。社会化とは、生後3週齢から12週齢頃までの大切な時期に、家族以外の人や他の犬、様々な物や音など、これから出会うであろうあらゆる刺激に慣れさせておくプロセスを指します。この時期に良い経験をたくさん積ませることで、未知のものに対する恐怖心や警戒心が和らぎ、過度に吠えることのない、落ち着いた成犬に育ちやすくなります。ワクチンプログラムが終わったら、ぜひパピークラスなどに参加してみましょう。
Q3. 無視をしても全く吠えやまない場合はどうすればいいですか?
無視をしても効果がない場合、いくつかの原因が考えられます。まず一つは、無視の仕方が不徹底である可能性です。ついチラッと見てしまったり、根負けして一度でも要求に応えてしまったりすると、犬は「粘れば構ってもらえる」と学習し、さらに吠えがエスカレートします。もう一つは、吠えの原因が「要求」ではなく、「警戒」や「恐怖」である場合です。この場合は無視では解決しないため、その原因を取り除くアプローチ(音に慣れさせる、怖い対象から遠ざけるなど)が必要になります。
Q4. 老犬になってから急に吠えるようになったのはなぜですか?
老犬が急に吠え始めた場合、身体的な不調や認知機能の低下が原因である可能性があります。例えば、関節の痛みや体のどこかの不快感を訴えていたり、視力や聴力が衰えたことによる不安から吠えているのかもしれません。また、人間と同じように認知症を発症し、昼夜が逆転して夜中に目的もなく吠え続けてしまう「夜鳴き」という症状が出ることもあります。これまでと様子が違うと感じたら、まずは動物病院を受診し、病的な原因がないかを調べてもらうことを強くお勧めします。
まとめ:吠える原因の理解が問題解決の第一歩。愛犬を信じて根気強く向き合おう
愛犬の吠えをやめさせるために最も大切なことは、その吠えの裏にある「気持ち」を理解しようと努めることです。犬は、私たちを困らせようとして吠えているわけではありません。警戒、要求、不安、喜び。その声には、必ず何かしらのメッセージが込められています。この記事で紹介したように、原因によって対処法は全く異なります。まずは愛犬をじっくりと観察し、なぜ吠えているのかを見極めることが、問題解決への最も確実な一歩となります。
しつけやトレーニングは、一朝一夕で成果が出るものではありません。時にはうまくいかずに、もどかしい思いをすることもあるでしょう。しかし、大切なのは、一貫した態度で、愛情を持って根気強く向き合い続けることです。飼い主さんが諦めずに寄り添えば、愛犬は必ずその気持ちに応えようとしてくれます。この記事が、あなたと愛犬との絆をより一層深め、穏やかで笑顔あふれる毎日を取り戻すための一助となれば幸いです。
大切なペットの移動にはペットタクシー「かるたく」がおすすめ

ペットタクシー「かるたく」は、愛玩動物飼養管理士の資格を持つドライバーが、大切なペットを安心・安全に送迎するサービスです。
動物病院への送迎が全体の55.9%を占め、ペットの体調に配慮した運転を心掛けています。料金は事前にシミュレーションでき、明瞭な価格設定が魅力です。車内は広々としており、多頭飼いの方も安心。
ペット用ラグジュアリークッションやスロープを完備し、快適な移動をサポートします。さらに、乗車毎の除菌・清掃・消臭を徹底し、清潔な環境を提供。
ペットホテル、引っ越し、トリミング、旅行など、さまざまなシーンでご利用いただけます。今なら最大50%オフのキャンペーン実施中。大切なペットとの移動に、ぜひ「かるたく」をご利用ください。