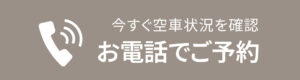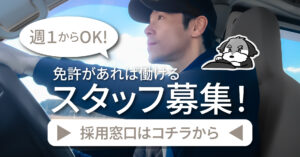「愛犬のハアハアが止まらない…もしかして熱中症?」夏の厳しい暑さが続く中、大切な家族である愛犬の体調を心配する飼い主さんは多いでしょう。犬の暑さ対策は、人間の対策とは少し違った知識が必要です。
この記事では、犬の熱中症の初期サインの見分け方、室内や散歩、留守番中といったシーン別の具体的な対策、さらには万が一の時の応急処置までを網羅的に解説します。
この記事を読めば、愛犬を夏の危険から守り、安全で快適な毎日を過ごすための知識がすべて手に入ります。
その症状、熱中症かも?愛犬にこんなサインはありませんか?

犬は言葉で「暑い」と伝えることができません。そのため、飼い主さんが普段と違う様子にいち早く気づいてあげることが非常に重要になります。
熱中症は進行が早く、命に関わることもある恐ろしい状態です。ここでは、熱中症の危険なサインをレベル別に分け、見逃すべきでないポイントを詳しく解説します。愛犬の小さな変化をキャッチできるよう、しっかりと確認しておきましょう。
初期症状を見逃さないで!危険度レベル別チェックリスト
犬の熱中症は、症状の重さによっていくつかの段階に分けられます。飼い主さんが初期症状の段階で気づき、迅速に対応することが愛犬の命を救う鍵となります。
軽度だからと油断せず、以下のリストに当てはまる症状が見られたら、すぐに対策を講じてください。特に複数の症状が同時に見られる場合は、危険度が高まっているサインです。日頃から愛犬の様子をよく観察し、ささいな変化も見逃さないようにしましょう。
レベル1(軽度):呼吸がいつもより速い、よだれが多い
熱中症の最も初期に見られるサインが、呼吸の変化です。犬は人間のように汗をかいて体温を下げることが苦手で、主に「パンティング」によって熱を逃がします。
パンティングとは、舌を出してハアハアと浅く速い呼吸をすることです。普段の運動後とは違う、激しく、落ち着きのないパンティングが続く場合は注意が必要です。
また、体温を下げるために血管が拡張し、よだれの量が異常に増えることもあります。この段階で涼しい場所へ移動させ、水分補給を行うことで、重症化を防ぐことができます。
レベル2(中度):ふらつき、ぐったりして元気がない、嘔吐や下痢
軽度の症状が進行すると、体温の上昇によって体内の機能に異常が出始めます。呼びかけへの反応が鈍くなったり、お気に入りのおもちゃを見せても興味を示さなくなったりするなど、明らかに元気がなくなります。
足元がおぼつかず、ふらふらと歩く「ふらつき」が見られる場合、脱水や脳への血流不足が疑われます。さらに、消化器官の機能も低下するため、嘔吐や下痢といった症状が現れることもあります。
これらのサインは体が限界に近づいている証拠であり、非常に危険な状態です。すぐに応急処置を開始し、動物病院へ連絡する準備をしてください。
レベル3(重度):意識がない、けいれん、舌の色が青紫色になる
これは命に危険が及んでいる緊急事態です。体温が極度に上昇すると脳に深刻なダメージを与え、呼びかけても反応しない「意識障害」や、全身がガクガクと震える「けいれん」発作を引き起こします。
さらに、血液中の酸素が不足し、舌や歯茎の色が普段のピンク色から青紫色に変わる「チアノーゼ」という状態に陥ります。
チアノーゼとは、血液中の酸素が欠乏した状態を示す危険なサインです。この段階になると、一刻の猶予もありません。体を冷やす応急処置を行いながら、すぐに動物病院へ連れて行き、緊急治療を受ける必要があります。
特に注意が必要な犬種や特徴|うちの子は大丈夫?
すべての犬が熱中症のリスクを抱えていますが、犬種や年齢、体型によっては特に注意が必要な子たちがいます。体の構造や機能的な特徴から、他の犬よりも体温調節が苦手なためです。
これは、生まれ持った特性なので、飼い主さんがその子の弱点を正しく理解し、環境を整えてあげることが不可欠です。
あなたの愛犬が以下の特徴に当てはまる場合は、より一層、慎重な暑さ対策を心がけてください。知っておくことで、防げるリスクは確実に存在します。
短頭種(フレンチブルドッグ、パグなど)
フレンチブルドッグやパグ、シーズーといった鼻が短い「短頭種」は、熱中症のリスクが非常に高い犬種です。短頭種は、鼻から喉にかけての気道が狭いという身体的な特徴を持っています。
この構造は、体温調節の要であるパンティングの効率を著しく低下させます。
つまり、一生懸命ハアハアと呼吸をしても、他の犬種ほどうまく体内の熱を外に逃がすことができないのです。少し暑い環境にいるだけでも体温が上がりやすいため、夏場はエアコンが効いた室内で過ごさせることが絶対条件となります。
北国原産の犬種(シベリアンハスキーなど)
シベリアンハスキーやサモエド、秋田犬など、寒い地域が原産の犬種も日本の夏は非常に苦手です。これらの犬種は、厳しい寒さから身を守るために、保温性に優れた厚い被毛を持っています。
この被毛は、アンダーコート(下毛)とオーバーコート(上毛)の二重構造になっており、「ダブルコート」と呼ばれます。
冬には非常に役立つこの分厚いコートが、夏場には熱を体に溜め込んでしまう原因となります。まるでダウンジャケットを着て夏を過ごしているようなものなので、こまめなブラッシングで抜け毛を取り除き、風通しを良くしてあげる必要があります。
子犬やシニア犬、肥満気味の犬
犬も人間と同じように、年齢によって体力が変化します。子犬はまだ体温調節機能が十分に発達しておらず、シニア犬は機能が衰えてきているため、暑さへの対応能力が低いです。
急激な気温の変化に対応しきれず、体調を崩しやすいため、飼い主さんによる細やかな管理が求められます。
また、肥満気味の犬も注意が必要です。首回りやお腹についた厚い皮下脂肪が断熱材のような役割を果たし、体内に熱がこもりやすくなります。さらに、心臓や呼吸器にも負担がかかるため、熱中症のリスクが格段に高まります。
【シーン別】今日からできる!愛犬を熱中症から守る具体的な暑さ対策

犬の暑さ対策は、ただ涼しくすれば良いという単純なものではありません。愛犬が一日を過ごす様々なシーンを想定し、それぞれに適した対策を講じることが重要です。
室内で快適に過ごすための工夫、危険が潜む留守番中の注意点、そして毎日の散歩や車での移動。それぞれの場面で飼い主さんが少し気を配るだけで、熱中症のリスクは大幅に減らすことができます。ここでは、具体的な対策をシーン別に分かりやすく紹介します。
①室内での対策:エアコンの最適温度と快適な環境づくり
夏の間、犬が最も多くの時間を過ごすのが室内です。飼い主さんが快適だと感じる温度でも、毛皮を着ている犬にとっては暑すぎることがあります。
犬が快適に過ごせる室内環境を維持することが、暑さ対策の基本中の基本と言えるでしょう。
特に、犬は自分でエアコンのスイッチを入れることはできません。飼い主さんが責任を持って、愛犬にとって安全で過ごしやすい空間を作り出してあげることが大切です。ここでは、室温管理のポイントを具体的に解説します。
エアコンの適切な温度は25〜28度、湿度は50%前後が目安
犬にとって快適な室温は、一般的に25〜28度が目安とされています。ただし、これはあくまで目安であり、愛犬の犬種、年齢、被毛の長さなどによって微調整が必要です。
例えば、暑さに弱い短頭種やシニア犬の場合は少し低めに、寒さに強い犬種の場合は少し高めに設定すると良いでしょう。
また、温度だけでなく湿度管理も非常に重要です。湿度が高いと、パンティングによる体温調節がうまくいかなくなり、熱中症のリスクが高まります。除湿機能を活用し、湿度を50%前後に保つように心がけてください。
サーキュレーターを併用して空気を循環させる
エアコンだけでは、冷たい空気が部屋の下の方に溜まってしまいがちです。床に近い場所で生活している犬のために、サーキュレーターを使って室内の空気を循環させましょう。
サーキュレーターとは、直線的で強い風を送り出すことで空気をかき混ぜる家電のことです。エアコンの冷気を部屋全体に効率的に行き渡らせることで、設定温度が同じでも体感温度を下げることができます。
犬の体に直接風が当たり続けると体調を崩す原因になるため、首振り機能を使ったり、壁や天井に向けて風を送ったりするのがおすすめです。
直射日光を防ぐ遮光カーテンやすだれの活用
窓から差し込む直射日光は、室温を上昇させる大きな原因となります。特に日当たりの良い部屋では、日中の日差しを遮る工夫をするだけで、エアコンの効きが格段に良くなります。
遮光カーテンやブラインド、すだれなどを活用して、日光が室内に直接入らないようにしましょう。
これにより、室温の上昇を抑えるだけでなく、床やケージが熱くなるのを防ぐ効果もあります。電気代の節約にも繋がるため、積極的に取り入れたい対策の一つです。
②留守番中の対策:最大の注意を払うべきポイント
飼い主さんが外出している間の留守番中は、犬にとって熱中症のリスクが最も高まる時間帯の一つです。犬は自分で環境を変えることができないため、飼い主さんが出かける前の準備がすべてを決めます。
「少しの時間だから大丈夫」という油断が、取り返しのつかない事態を引き起こす可能性があります。
愛犬が安全に留守番できるよう、万全の対策を講じておくことが飼い主の責任です。ここでは、留守番中に必ず守ってほしいポイントを解説します。
エアコンは絶対につけっぱなしにする
夏の留守番において、電気代を気にしてエアコンを消したり、タイマーを設定したりするのは絶対にやめてください。タイマーが切れた後に室温が急上昇し、犬が熱中症になってしまう事故が後を絶ちません。
たとえ短時間の外出であっても、天気予報が外れて急に気温が上がる可能性も考えられます。
愛犬の命を守ることを最優先に考え、留守番中は必ずエアコンをつけっぱなしにして室温を一定に保つようにしましょう。万が一の停電に備え、クールマットなども併用するとさらに安心です。
いつでも新鮮な水が飲めるよう複数の場所に設置する
留守番中は、水分補給が非常に重要になります。万が一、一つの水飲みボウルをひっくり返してしまっても大丈夫なように、水飲み場は必ず2ヶ所以上に設置してください。
給水ボトルとボウルを併用するのも良い方法です。また、長時間家を空ける場合は、水がぬるくなったり汚れたりしないように、出発前に新鮮な水に取り替えてあげましょう。
自動給水器を利用すれば、常に新鮮な水が循環するため、犬も喜んで水を飲んでくれるでしょう。脱水は熱中症の引き金になるため、水分補給対策は万全にしておきましょう。
クールマットやアルミプレートを用意しておく
エアコンをつけていても、犬は自分で最も快適な場所を探して移動します。犬が自分の判断で体を冷やせるように、クールマットやアルミプレートなどを部屋に置いてあげましょう。
クールマットには、ジェルタイプや接触冷感生地のものなど様々な種類があります。
犬が噛んで中身を誤飲する危険性がないか、素材の安全性も確認して選ぶことが大切です。これらのグッズを用意しておくことで、犬は暑いと感じた時に自分で涼むことができ、快適に留守番をすることができます。
③散歩での対策:時間帯とアスファルトの温度に注意
犬にとって散歩は、運動不足の解消やストレス発散に欠かせない大切な時間です。しかし、夏の散歩は時間帯や場所を間違えると、熱中症や肉球のやけどといった危険が伴います。
特に、日中のアスファルトは非常に高温になり、犬の体に大きな負担をかけます。安全に散歩を楽しむためには、飼い主さんが細心の注意を払う必要があります。
ここでは、夏の散歩で気をつけるべきポイントを具体的に解説します。楽しい散歩の時間にするために、しっかりと対策をしましょう。
散歩は早朝や日が暮れた涼しい時間帯に
夏の散歩は、時間帯選びが最も重要です。日中の散歩は絶対に避け、比較的涼しい早朝(日の出前後)や、日が完全に沈んで地面の熱が冷めた夜間に行うようにしてください。
たとえ曇りの日でも、日中は気温も湿度も高く、熱中症のリスクがあります。
また、アスファルトは太陽の熱を吸収しやすいため、夕方でもまだ熱が残っていることが多いです。散歩に出る前には、必ず外の気温と湿度を確認し、無理のない計画を立てることが大切です。愛犬の健康を第一に考え、散歩の時間を調整しましょう。
地面を触って熱くないか必ず確認する
人間は靴を履いていますが、犬は素足で地面を歩きます。夏の直射日光を浴びたアスファルトは、目玉焼きが焼けるほどの高温(60度以上)になることもあり、犬の肉球をやけどさせてしまう危険があります。
散歩に出る前には、必ず飼い主さん自身が手の甲で5秒間地面を触ってみてください。もし「熱い」と感じるようであれば、散歩には適していません。
アスファルトだけでなく、マンホールや金属製の側溝の蓋なども高温になるため、注意が必要です。できるだけ土や草の上を歩かせるなどの配慮も大切です。
こまめな水分補給とクールグッズの活用
夏の散歩は、たとえ短い時間であっても犬の体力を消耗させます。脱水症状を防ぐために、散歩中もこまめに水分補給ができるよう、必ず飲み水を持参しましょう。
携帯用の給水ボトルや折りたたみ式の水飲みボウルなど、便利なグッズがたくさんあります。
また、散歩に出かける前に、水で濡らして使うクールウェアを着せたり、首にクールバンダナを巻いてあげたりするのも非常に効果的です。これらのグッズは、気化熱を利用して犬の体温上昇を緩やかにしてくれます。
④車での移動・ドライブでの対策:短時間でも絶対に油断しない
夏場の車内は、短時間で驚くほど高温になり、熱中症を引き起こす非常に危険な空間となります。JAF(日本自動車連盟)のテストによると、気温35度の日にエンジンを停止させた車内は、わずか15分で人体に危険なレベルまで温度が上昇するという結果が出ています。
「コンビニに寄るだけ」「少しだから大丈夫」といった軽い気持ちが、愛犬の命を奪うことになりかねません。
車でのお出かけが増える季節だからこそ、正しい知識を持って安全対策を徹底することが求められます。
短時間でも絶対に車内に置き去りにしない
夏の車内への犬の置き去りは、虐待行為と言っても過言ではありません。「窓を少し開けておけば大丈夫」「日陰に停めたから平気」といった考えは、全く通用しないことを肝に銘じてください。
窓を数センチ開けた程度では車内温度の上昇をほとんど防ぐことはできず、日陰であっても時間の経過とともに日が当たる場所に変わってしまいます。
飼い主さんが車を離れる際は、たとえ1分であっても必ず愛犬を一緒に連れて行くか、誰かが車内に残ってエアコンをつけ続けるなど、絶対的な安全を確保してください。
後部座席にもエアコンの風が届くように工夫する
クレートやキャリーバッグに入れて後部座席に乗せている場合、運転席で感じる温度と犬がいる場所の温度が違うことがあります。特にミニバンやSUVなど車内が広い車では、後部座席までエアコンの冷気が届きにくい場合があります。
犬が暑がっていないか、こまめに様子を確認してあげましょう。
対策として、車用のミニサーキュレーターを設置して後部座席に風を送ったり、サンシェードで窓からの直射日光を遮ったりするのが効果的です。また、凍らせたペットボトルをタオルで巻いてクレートのそばに置いてあげるのも良いでしょう。
出発前に車内を十分に冷やしておく
炎天下に駐車していた車に乗り込む際は、人間でも息苦しさを感じるほど熱がこもっています。犬を乗せる前に、まず車のドアを全開にして熱気を逃がし、エアコンを外気導入にして車内の熱い空気を外に出してから、犬を乗せるようにしましょう。
ある程度車内が涼しくなってから、エアコンを内気循環に切り替えると効率的に冷やすことができます。
出発前のほんの少しの準備で、犬への負担を大きく減らすことができます。特に暑さに弱い犬種の場合は、より慎重な配慮が必要です。
【目的別】獣医師も推薦!本当に役立つ犬の暑さ対策グッズ8選

近年、犬用の暑さ対策グッズは非常に多様化しており、どれを選べば良いか迷ってしまう飼い主さんも多いでしょう。大切なのは、愛犬のライフスタイルや使用するシーンに合わせて、最適なグッズを選ぶことです。
ここでは、「室内・留守番用」と「散歩・お出かけ用」の2つの目的に分け、数あるグッズの中から獣医師の視点でも推奨できる、本当に役立つアイテムを厳選してご紹介します。それぞれのグッズのメリット・デメリットも理解し、賢く活用しましょう。
室内・留守番で活躍する「設置型」ひんやりグッズ
エアコンによる室温管理を基本としながら、補助的にひんやりグッズを活用することで、より快適で安全な室内環境を作ることができます。特に、犬が自分の意志で涼しい場所を選べるようにしておくことは、留守番中の熱中症対策として非常に重要です。
また、万が一の停電時にも、こうしたグッズがあるだけで愛犬の命を救える可能性があります。ここでは、室内での使用におすすめの「設置型」グッズを紹介します。
定番のクールマット・ひんやりベッド
クールマットやベッドは、犬が手軽に涼をとれる定番アイテムです。素材には様々な種類があり、それぞれの特徴を理解して選ぶことが大切です。
例えば、「ジェルタイプ」は冷却効果が高いですが、犬が噛んで破損させると中身を誤飲する危険性があります。「接触冷感生地」のものは、触れるとひんやりと感じる素材でできており、安全性は高いですが冷却効果の持続時間は短めです。愛犬の性格(噛み癖など)や、どれくらいの涼しさを求めるかに合わせて選びましょう。
水も電気も使わないクールアルミシート
クールアルミシート(プレート)は、犬の体熱を吸収して空気中に放熱する性質を持つアルミニウム製の板です。電気や水を使わないため、留守番中も安全で、経済的なのが最大のメリットです。
また、汚れが染み込みにくく、サッと拭くだけで手入れができるため衛生的に使えます。
ただし、フローリングなどの硬い床に直接置くと滑りやすいことや、アルミの硬い感触を嫌がる犬もいる点がデメリットとして挙げられます。滑り止めが付いている製品を選んだり、最初は薄いタオルを敷いて慣れさせたりすると良いでしょう。
停電時にも安心な自然凍結タイプのネッククーラー
最近注目されているのが、特殊な素材(PCM素材)を使い、28度以下の環境で自然に凍結するネッククーラーです。冷凍庫に入れなくても涼しい場所に置いておくだけで繰り返し使えるため、停電時や災害時にも役立つと人気を集めています。
冷却効果が穏やかで、冷えすぎる心配がないのも安心なポイントです。
留守番中に首輪代わりに着けておけば、エアコンが止まってしまった場合のお守り代わりになります。ただし、製品によって持続時間が異なるため、留守番の時間に合わせて選ぶ必要があります。
散歩・お出かけで重宝する「装着&携帯型」クールグッズ
夏の散歩やお出かけでは、室内とは違った暑さ対策が求められます。照りつける日差しや熱くなった地面から愛犬を守り、外出先でも水分補給ができるように準備しておくことが不可欠です。
ここでは、持ち運びができて、屋外での活動をサポートしてくれる「装着&携帯型」の便利グッズを紹介します。これらのグッズを上手に活用して、夏のアウトドアを安全に楽しみましょう。
水で濡らすだけで使えるクールウェア・クールベスト
クールウェアやクールベストは、夏の散歩の必需品とも言えるアイテムです。水で濡らして軽く絞ってから着せるだけで、水分が蒸発する際の気化熱を利用して犬の体を冷やす仕組みです。
日差しを直接浴びるのを防ぎ、紫外線対策になるというメリットもあります。
選ぶ際は、犬の体にフィットするサイズであること、動きを妨げないデザインであることが重要です。ただし、湿度の高い日には水が蒸発しにくく効果が薄れることや、生乾きのまま放置すると雑菌が繁殖しやすい点には注意が必要です。
首元を冷やすクールバンダナ・ネッククーラー
犬の首には、太い血管が皮膚に近いところを通っています。そのため、首元を冷やすことは、体全体を効率良くクールダウンさせるのに非常に効果的です。
クールバンダナやネッククーラーは、手軽に装着できる便利なアイテムです。
水で濡らすタイプや、中に保冷剤を入れるタイプなどがあります。保冷剤を入れるタイプは冷却効果が高いですが、凍傷にならないよう、保冷剤が直接皮膚に当たらない製品を選びましょう。散歩の時だけでなく、ドライブ中の車内で使うのもおすすめです。
シャワー機能付きもある携帯給水ボトル
夏の外出時の水分補給は絶対に欠かせません。犬用の携帯給水ボトルは、飲み皿とボトルが一体化しており、片手で手軽に水を与えられるため非常に便利です。
最近では、飲み水としてだけでなく、ボトルの先端からシャワーのように水を出せる製品も人気です。
この機能を使えば、散歩中に犬の体に水をかけてあげたり、排泄後のおしっこを洗い流したりすることもできます。一つ持っておくと様々な場面で役立つ、夏のお出かけのマストアイテムと言えるでしょう。
万が一のために!熱中症が疑われる場合の応急処置と対処法

どれだけ気をつけていても、愛犬が熱中症になってしまう可能性はゼロではありません。大切なのは、その「万が一」の時に飼い主さんがパニックにならず、落ち着いて行動することです。
熱中症は時間との勝負であり、動物病院に到着するまでの応急処置がその後の回復を大きく左右します。ここでは、愛犬に熱中症の疑いがある場合に、飼い主さんが自宅やその場ですべきことを具体的に解説します。正しい知識が、愛犬の命を救います。
まずは涼しい場所へ!応急処置の3ステップ
愛犬の様子がおかしいと感じたら、ためらわずにすぐに行動を開始してください。熱中症の応急処置で最も重要なのは、とにかく早く体温を下げることです。
これから紹介する3つのステップを、落ち着いて、迅速に行ってください。
ただし、これらの処置はあくまで動物病院へ行くまでのつなぎであり、自己判断で治療を終えてはいけないことを忘れないでください。必ず、応急処置と並行して動物病院へ連絡し、指示を仰ぎましょう。
①すぐに涼しい場所(室内など)へ移動させる
熱中症の疑いがある場合、まず最初にすべきことは、その原因となっている暑い環境から愛犬を避難させることです。散歩中であれば日陰や近くの建物の中へ、室内であればエアコンが効いた涼しい部屋へすぐに移動させてください。
体をさらに熱くする原因から一刻も早く遠ざけることが、応急処置の第一歩です。この時、犬を無理に歩かせると体力を消耗させてしまうため、可能であれば抱きかかえて運んであげましょう。
②体を冷やす(濡れタオルや保冷剤を首や脇、股関節に当てる)
涼しい場所へ移動したら、次は積極的に体温を下げる処置を行います。水道水で濡らしたタオルを体全体にかけたり、霧吹きで水を吹きかけたりして、体に風を当てて熱を逃がします。
この時、冷たすぎる氷水を使うと血管が収縮してしまい、かえって熱が体内にこもってしまうため、常温の水を使用してください。
さらに、保冷剤や氷嚢をタオルで包み、首の付け根や脇の下、足の付け根(股関節)など、太い血管が通っている場所を冷やすとより効果的です。
③水分を補給させる(無理に飲ませない)
脱水症状を緩和するために、水分を補給してあげることも大切です。ただし、犬が自力で水を飲める状態かどうかを慎重に判断してください。
意識が朦朧としている場合や、ぐったりして起き上がれない状態の時に無理に水を飲ませようとすると、誤って気管に入ってしまう「誤嚥(ごえん)」を引き起こす危険があります。
もし犬が自分で水を飲もうとしない場合は、無理強いは絶対にせず、口の周りを湿らせてあげる程度に留め、すぐに動物病院へ向かいましょう。
ためらわずに動物病院へ!受診すべき危険なサイン
応急処置によって愛犬の症状が少し落ち着いたように見えても、絶対に油断してはいけません。熱中症は、見た目以上に体内の臓器に深刻なダメージを与えている可能性があります。
一度上がった体温によってダメージを受けた臓器は、後から時間差で機能不全に陥ることも少なくありません。
応急処置はあくまで緊急避難的な対応であり、治療ではないことを理解してください。特に、嘔吐や下痢が続く、ぐったりして動かない、けいれんを起こしたといった場合は、極めて危険な状態です。必ず動物病院を受診し、獣医師による適切な診断と治療を受けさせてください。
犬の暑さ対策に関するよくある質問
ここまで犬の暑さ対策について詳しく解説してきましたが、飼い主さんからは日々様々な質問が寄せられます。ここでは、特に多くの方が疑問に思う点や、誤解されがちなポイントについて、Q&A形式で分かりやすくお答えします。正しい知識を身につけ、愛犬との夏をより安全に過ごすための参考にしてください。
扇風機だけつけて留守番させても大丈夫ですか?
結論から言うと、扇風機だけでの留守番は非常に危険であり、熱中症対策にはなりません。人間は汗をかき、その汗が蒸発する時に気化熱で体温が下がるため、扇風機の風を涼しく感じます。
しかし、犬は足の裏などごく一部にしか汗をかきません。そのため、犬に扇風機の風を当てても、熱風を送られているのと同じで、体温を下げる効果はほとんど期待できないのです。夏の留守番は、必ずエアコンを使用して室温そのものを下げることが絶対条件です。
愛犬に氷や冷たい水を与えてもいいですか?
暑そうにしている愛犬を見ると、氷や冷たい水を与えたくなるかもしれません。少量であれば問題ありませんが、与えすぎには注意が必要です。
急に冷たいものを大量に摂取すると、胃腸に負担をかけて下痢や嘔吐を引き起こすことがあります。
特に、熱中症でぐったりしている時に氷を丸ごと与えるのは、喉に詰まらせる危険性もあるため避けるべきです。普段の水分補給として与える場合は、数個のかけらを水に浮かべてあげる程度に留めておきましょう。
サマーカットは暑さ対策に効果がありますか?
被毛を短くするサマーカットには、メリットとデメリットの両方があります。メリットは、皮膚の通気性が良くなり熱がこもりにくくなることや、お手入れが楽になる点です。
一方で、デメリットもあります。被毛には、強い日差しや紫外線から皮膚を守るという重要な役割があります。
被毛を短く刈り込みすぎると、このバリア機能が失われ、直射日光で皮膚がやけどしたり、紫外線のダメージを直接受けたりするリスクが高まります。また、虫に刺されやすくなることもあります。サマーカットをする場合は、バリカンで短くしすぎず、数センチの長さを残すようにトリマーさんと相談しましょう。
外飼いの犬のためにできる暑さ対策はありますか?
近年は室内飼いが主流ですが、やむを得ず外で飼育している場合、夏場の暑さ対策はより深刻な課題となります。理想を言えば、夏の間だけでも玄関や涼しい部屋に入れるなど、室内へ避難させてあげるのが最も安全です。
それが難しい場合は、犬小屋が一日中日陰になるように、すだれや遮光ネットなどで日よけを設置してください。
また、地面に打ち水をして温度を下げたり、新鮮な水をいつでも飲めるように複数用意したりといった対策は必須です。凍らせたペットボトルを数本置いてあげるのも良いでしょう。
まとめ:正しい知識と万全の対策で、愛犬と安全で楽しい夏を過ごそう
ここまで、犬の熱中症のサインから具体的な暑さ対策、そして緊急時の対処法までを詳しく解説してきました。犬の暑さ対策で最も大切なことは、「犬は人間以上に暑さに弱い」という事実を飼い主さんが深く理解し、先回りして環境を整えてあげることです。
エアコンによる室温管理を徹底し、散歩の時間帯に気を配り、留守番や車での移動に細心の注意を払う。
こうした日々の小さな積み重ねが、愛犬を熱中症という命の危険から守ります。この記事で得た知識を今日から実践し、かけがえのない家族である愛犬と、安全で思い出深い夏を過ごしてください。
大切なペットの移動にはペットタクシー「かるたく」がおすすめ

ペットタクシー「かるたく」は、愛玩動物飼養管理士の資格を持つドライバーが、大切なペットを安心・安全に送迎するサービスです。
動物病院への送迎が全体の55.9%を占め、ペットの体調に配慮した運転を心掛けています。料金は事前にシミュレーションでき、明瞭な価格設定が魅力です。車内は広々としており、多頭飼いの方も安心。
ペット用ラグジュアリークッションやスロープを完備し、快適な移動をサポートします。さらに、乗車毎の除菌・清掃・消臭を徹底し、清潔な環境を提供。
ペットホテル、引っ越し、トリミング、旅行など、さまざまなシーンでご利用いただけます。今なら最大50%オフのキャンペーン実施中。大切なペットとの移動に、ぜひ「かるたく」をご利用ください。