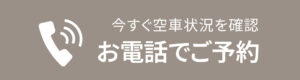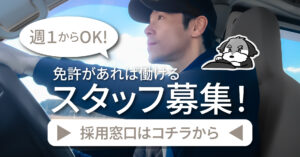猫を愛する飼い主の皆さん、日々の猫砂の捨て方で「これって燃えるゴミでいいのかな?」「トイレに流せるタイプだけど、本当に大丈夫?」と迷った経験はありませんか。
間違った捨て方は、不快な臭いの原因になったり、ご近所トラブルに繋がったりする可能性もあり、不安に感じる方も少なくありません。
この記事では、猫砂の正しい捨て方を素材別に徹底解説します。
さらに、トラブルを避けるための「トイレに流す際」の重要注意点から、ゴミの日まで臭わせないプロの保管術まで、専門家の視点で分かりやすく紹介します。
この記事を最後まで読めば、あなたの疑問や不安はすべて解消され、自信を持って正しく猫砂を処理できるようになるでしょう。
まずは結論!あなたの猫砂、どう捨てるべき?一目でわかるフローチャート

猫砂の捨て方に迷ったら、まず結論からお伝えします。
猫砂の捨て方は「猫砂の素材」と「お住まいの自治体のルール」という、たった2つのポイントで決まります。
なぜなら、猫砂の主原料によってゴミの基本的な分類(燃えるゴミか、燃えないゴミか)が異なり、その最終的な処分方法は各市区町村が定めたルールに従う必要があるからです。
この2つのポイントさえ押さえれば、間違うことはありません。
以下のフローチャートを使えば、ご自身のケースに合った捨て方が一目で分かります。
日々のトイレ掃除の際に、ぜひ役立ててください。
猫砂の捨て方 判断フローチャート
| START |
| ↓ |
| Q1. お使いの猫砂の素材は何ですか? |
| ├→ 鉱物・シリカゲル → Q2へ |
| └→ 紙・おから・木 → Q3へ |
| ↓ |
| Q2.【鉱物・シリカゲル系の場合】 |
| 多くは「燃えないゴミ」です。ただし、必ずお住まいの自治体のルールを確認してください。 |
| ↓ |
| Q3.【紙・おから・木系の場合】 |
| 多くは「燃えるゴミ」です。製品によってはトイレに流せますが、Q4へ進んでください。 |
| ↓ |
| Q4. トイレに流せるタイプですか? |
| ├→ NO → 「燃えるゴミ」として捨ててください。 |
| └→ YES → Q5へ |
| ↓ |
| Q5. 自治体やマンションの規約で流すことが許可されていますか? |
| ├→ NO → ルールに従い「燃えるゴミ」として捨ててください。 |
| └→ YES → 製品の指示を守り、少量ずつ流してください。少しでも不安なら燃えるゴミが安全です。 |
【素材別】猫砂の捨て方早見表|燃えるゴミ?燃えないゴミ?

猫砂には様々な種類の素材があり、それぞれ捨て方の基本が異なります。
ご自身の愛猫が使っている猫砂がどのタイプに当てはまるかを確認し、正しい分別方法を把握しましょう。
ここでは代表的な5つの素材について、一般的なゴミの分類を分かりやすく解説します。
①鉱物系(ベントナイトなど):多くの自治体で「燃えないゴミ」
鉱物系の猫砂は、多くの場合「燃えないゴミ」として処分する必要があります。
主成分が「ベントナイト」という粘土鉱物の一種であり、自然界の土や砂と同じ扱いになるため、燃えないゴミに分類されるのが一般的です。
ベントナイトとは、水分を吸収すると強く固まる性質を持つ粘土のことで、猫の尿をしっかりと固めて処理しやすくしてくれます。
例えば、東京都新宿区や横浜市など、多くの主要都市で燃えないゴミに指定されています。
ただし、自治体によっては独自のルールを設けている場合もあるため、製品パッケージの表示だけでなく、必ずお住まいの地域のルールを優先して正しく分別しましょう。
②紙系:基本的に「燃えるゴミ」だが注意点も
再生パルプなどを原料とする紙製の猫砂は、基本的に「燃えるゴミ」として捨てることが可能です。
主原料が紙であるため、可燃物に分類されるのがその理由です。
素材が軽く、比較的安価な製品が多いため、処理のしやすさや経済的な負担の軽さが大きなメリットといえるでしょう。
ただし、消臭効果を高めるために鉱物系の粉末などが混ぜられている製品も存在します。
製品のパッケージに「燃えるゴミOK」といった表示があるかを確認するとより安心です。
もちろん、最終判断は自治体の分別ルールに従うことが大切なので、合わせて確認する習慣をつけましょう。
③おから系:「燃えるゴミ」や「トイレに流せる」タイプが多い
食品であるおからを主原料とする猫砂は、「燃えるゴミ」として捨てられるのが一般的です。
その理由は、原料が豆腐を作る際に出る食品由来のものであり、環境に優しく自然に分解されやすいため、可燃物として扱われるからです。
万が一猫が口にしてしまっても安全性が高いことから、人気の素材の一つとなっています。
製品によっては、トイレに流せることを特徴としているものも多く販売されています。
しかし、トイレに流す場合は後ほど詳しく解説する重要な注意点がありますので、安易な判断は禁物です。
最もトラブルが少なく安全な方法は、燃えるゴミとして出すことだと覚えておきましょう。
④木系(木質ペレットなど):「燃えるゴミ」が一般的
間伐材やひのき、松などを原料とする木系の猫砂は、ほとんどの場合「燃えるゴミ」として処分できます。
木材チップや、木粉を圧縮して固めた「木質ペレット」が主成分であり、燃やすことが可能な素材だからです。
自然由来のさわやかな香りで、化学的な香りが苦手な飼い主さんや猫にも好まれる傾向があります。
おから系と同様に、製品によってはトイレに流せるとされているものも存在します。
しかし、木のチップは水に溶けにくい性質を持つため、排水管の詰まりのリスクは十分に考慮すべきです。
基本は燃えるゴミとして、確実で安全な方法で処分するのが最もおすすめです。
⑤シリカゲル系:多くは「燃えないゴミ」として処分
強力な消臭力と吸収力が特徴のシリカゲル系猫砂は、多くの場合「燃えないゴミ」に分類されます。
その理由は、主成分のシリカゲルが、ガラスの原料でもある二酸化ケイ素から作られており、燃えない性質を持つためです。
シリカゲルとは、表面に無数の小さな穴が開いた多孔質の物質で、強い吸湿性を持ちます。お菓子の袋などに入っている乾燥剤をイメージすると分かりやすいでしょう。
尿を吸収しても固まらず、交換頻度が少なくて済むというメリットがあります。
しかし、捨てる際は鉱物系と同様に、燃えないゴミとして出すよう定めている自治体がほとんどですので、必ずルールを確認して正しく処分しましょう。
ちょっと待って!「トイレに流せる猫砂」を捨てる際の3つの重要注意点

「トイレに流せる」と書かれた猫砂は、ゴミ出しの手間が省けてとても便利に感じます。
しかし、安易に流してしまうと、修理に高額な費用がかかる深刻なトラブルに繋がる可能性があります。
大切な愛猫との暮らしを守り、近隣に迷惑をかけないためにも、以下の3つの注意点を必ず守ってください。
①自治体のルールが最優先!下水道局の方針を確認
製品パッケージに「流せる」と記載があっても、お住まいの自治体が許可していなければトイレに流してはいけません。
なぜなら、自治体によっては、下水管の詰まりや下水処理施設への過度な負荷を理由に、猫砂を含む固形物をトイレに流すことを条例などで禁止している場合があるからです。
製品メーカーの表示よりも、自治体のルールが常に優先されます。
例えば、東京都下水道局は、ペットのフンや猫砂をトイレに流さないよう公式ウェブサイトで明確に呼びかけています。
トラブルを避けるため、まずはご自身の自治体の「下水道局」の公式見解を確認することが最も重要です。
②マンション等の集合住宅では管理規約を必ずチェック
集合住宅の場合、自治体のルールとは別に、マンション独自の管理規約で猫砂を流すことが禁止されている場合があります。
その理由は、集合住宅の排水管は多くの世帯が共有しており、構造が複雑なため戸建て住宅よりも詰まりのリスクが高いからです。
一度詰まると、自分の部屋だけでなく階下の部屋にまで水漏れなどの甚大な被害が及ぶ可能性があります。
入居時に受け取った書類や、管理組合からのお知らせなどを必ず確認しましょう。
もし不明な場合は、自己判断せず、必ず管理会社や大家さんに問い合わせることが大切です。
損害賠償問題に発展するケースも考えられるため、細心の注意を払いましょう。
③詰まりを防ぐ!一度に流す量と水量のルール
もし自治体やマンションで流すことが許可されていても、製品に記載された「一度に流せる量」と「流し方のルール」を厳守する必要があります。
一度に大量に流してしまうと、いくら水に溶けやすいとされる猫砂でも完全に溶けきらず、排水管のカーブ部分などに溜まって詰まりの原因になるからです。
これは絶対に避けなければなりません。
「1回につき、固まり1個まで」「必ず『大』の水流で流す」など、製品ごとに細かい指示が記載されています。
特に、近年の節水型トイレは流れる水量が少ないため、詰まりのリスクがより高まる傾向にあります。
少しでも不安を感じる場合は、燃えるゴミとして捨てるのが最も賢明な判断です。
プロが実践する!ゴミの日まで臭わせない猫砂の捨て方&保管術

猫のトイレ掃除で一番の悩みは、やはり「臭い」ではないでしょうか。
ゴミの日まで、不快な臭いを部屋に充満させないための簡単なコツが存在します。
ここでは、誰でもすぐに実践できるプロの臭い対策と、スマートな保管術を紹介します。
①臭いの元を断つ!フンと尿の正しい処理方法
臭い対策の基本は、フンと尿で固まった砂を、できるだけ早くトイレから取り除くことです。
フンや尿は、時間が経つにつれて雑菌が繁殖し、アンモニアなどの強い刺激臭を発生させます。
こまめに掃除することが、臭いの発生源を根本から断つ最も効果的で重要な方法なのです。
最低でも1日1〜2回、愛猫がトイレをした後に掃除するのが理想的です。
フンは専用のスコップで丁寧に取り除き、尿で固まった部分は周りのきれいな砂を余計に巻き込まないように、少し大きめにすくい取るのがコツです。
こまめなトイレ掃除を習慣化し、快適な室内環境を保ちましょう。
②専用の防臭袋や新聞紙を活用した密閉テクニック
処理した猫砂は、臭いが漏れ出さないように、しっかりと袋を密閉して捨てることが重要です。
ただのビニール袋では、目に見えない臭いの分子が袋の素材を透過してしまいます。
臭いを強力に閉じ込める機能を持つ専用の袋を使うことで、ゴミ箱からの不快な臭い漏れを劇的に減らすことが可能です。
ペット用の防臭袋(BOSなど)や、赤ちゃんの使用済みおむつ用の袋は、特殊な素材で作られており非常に高い効果を発揮します。
また、新聞紙に一度包んでから袋に入れると、新聞紙が湿気と臭いを吸収してくれるため、さらに効果が高まるのでおすすめです。
③おすすめのフタ付きゴミ箱と置き場所の工夫
猫砂専用のゴミ箱を用意し、フタがしっかりと閉まる密閉性の高いものを選ぶのがおすすめです。
フタがあることで、万が一袋から漏れ出てしまった臭いを物理的に閉じ込めることができます。
特に、フタの縁にゴムパッキンが付いているタイプのゴミ箱なら、さらに高い防臭効果が期待できるでしょう。
おむつ処理用のペールは、臭いが漏れにくい特殊な構造になっている製品が多く、猫砂用としても非常に人気があります。
ゴミ箱の置き場所は、可能であれば風通しの良いベランダや玄関などが理想です。
室内に置く場合は、ゴミ箱の底に消臭剤や重曹を敷いておくなどの工夫も有効です。
【必須作業】お住まいの地域の捨て方を確認する方法

これまで素材別の捨て方の基本を解説してきましたが、最終的なルールを決めているのは、常にお住まいの自治体です。
引越しをした際や、ルールに迷った際に、正確な情報を得るための具体的な方法を3つ紹介します。
この方法を知っておけば、もう迷うことはありません。
①一番確実!自治体の公式サイトやごみ分別アプリで調べる
最も正確で信頼できる情報は、お住まいの自治体の公式ウェブサイトや、自治体が提供しているごみ分別アプリにあります。
その理由は、自治体が直接発信する情報は公的なものであり、常に最新の正しいルールが掲載されているからです。
インターネット上の不確かな情報に惑わされ、誤った方法で処分してしまうリスクを完全になくすことができます。
自治体のサイト内にある「ごみ」「暮らし」「環境」などのページを探し、「ごみ分別辞典」や「品目別収集区分一覧」といった項目を確認しましょう。
「猫砂」と検索すれば、該当のページがすぐに見つかることが多いです。
②「〇〇市 ごみ 猫砂」で検索して情報を探す
手軽に調べたい場合は、検索エンジンで「(お住まいの市区町村名) ごみ 猫砂」と検索する方法が便利です。
この検索方法を使うと、自治体の公式サイトの該当ページや、地域の情報に詳しい個人のブログなどが検索結果の上位に表示されやすくなります。
そのため、素早く目的の答えにたどり着ける可能性が高いでしょう。
例えば「新宿区 ごみ 猫砂」と検索すると、新宿区の公式サイトや分別に関する情報ページがすぐに見つかります。
ただし、個人ブログの情報は古かったり、誤っていたりする場合もあるため、最終的には公式サイトで裏付けを取るとより確実です。
③迷ったら環境課・清掃課に電話で問い合わせる
ウェブサイトを見ても分からない、あるいは特殊なケースで判断に迷う場合は、役所の担当部署に直接電話で問い合わせるのが最も確実です。
その理由は、担当者が直接、正確な分別方法や捨て方の注意点を具体的に教えてくれるため、あらゆる疑問をその場で解消できるからです。
曖昧なまま捨ててしまうという精神的な不安からも解放されます。
市区町村の役所の代表電話にかけ、「ごみの分別についてお伺いしたい」と伝えれば、環境課や清掃課といった担当部署につないでもらえます。
問い合わせる際は、使っている猫砂の素材(鉱物、紙など)を事前に伝えると、話がスムーズに進むでしょう。
猫砂の捨て方に関するよくある質問
ここまで猫砂の捨て方の基本を解説してきましたが、ほかにも細かい疑問や気になる点があるかと思います。
ここでは、飼い主さんから特によく寄せられる質問について、分かりやすいQ&A形式でお答えします。
Q1. 猫のうんちはトイレに流して、砂だけ捨てても良いですか?
A. 健康な猫のうんちであれば、トイレに流せる場合が多いですが、これも自治体の方針によります。
うんちの周りについている猫砂は、できるだけきれいに取り除いてから流すのが原則です。
ただし、下痢をしている時や寄生虫の心配がある場合は、他の猫や人間への感染を防ぐためにもトイレには流さず、燃えるゴミとして捨てるのが衛生的です。
東京都のようにペットのフン全般をトイレに流さないよう指導している自治体もあるため、やはりお住まいの地域のルール確認が基本となります。
Q2. 古い猫砂を全量交換する時など、大量に捨てる場合の注意点はありますか?
A. 一度に大量の猫砂をゴミとして出す場合は、まず自治体のルールを確認する必要があります。
自治体によっては、「一回に出せるゴミの量は45L袋で〇袋まで」といった具体的な決まりがあるからです。
ルールを超える量を出す場合は、「臨時ゴミ」や「粗大ゴミ」扱いとなり、有料での収集申込みが必要になることがあります。
また、重くなりすぎると収集作業員の方の大きな負担になるため、何回かに分けて出すといった配慮も大切です。
Q3. ベランダや庭の土に猫砂を埋めても問題ないですか?
A. フンや尿の混ざった猫砂を土に埋めるのは、衛生面や環境面から絶対にやめましょう。
猫のフンには、「トキソプラズマ」などの人間に感染する可能性のある寄生虫や細菌が含まれていることがあります。
土壌や地下水を汚染するだけでなく、悪臭や害虫の発生により、ご近所トラブルの原因にもなりかねません。
おからや木など自然素材の猫砂であっても、使用済みのものは自治体のルールに従ってゴミとして処分してください。
Q4. 猫砂を捨てるのにおすすめのゴミ袋はありますか?
A. 臭いを徹底的に防ぎたいなら、特殊な防臭素材で作られたペット用の防臭袋が最もおすすめです。
特に「BOS(ボス)」などの有名ブランドは、多くの飼い主さんから高い評価を得ています。
コストを抑えたい場合は、赤ちゃんの使用済みおむつ用の袋も同様の効果が期待できるでしょう。
普段使いとしては、中身が見えないように黒などの色付きのビニール袋を二重にするだけでも、ある程度の臭いと袋の強度を確保できます。
まとめ:正しい捨て方で猫も人も快適なトイレライフを実現しよう

猫砂の正しい捨て方をマスターすることは、愛猫との快適で衛生的な暮らしに直結する、非常に大切な飼い主の努めです。
なぜなら、正しい処分を心がけることは、室内の不快な臭いを防ぐだけでなく、自治体のルールを守り、ご近所との無用なトラブルを避けることにも繋がるからです。
何よりも、常に清潔なトイレ環境を保つことは、きれい好きな猫自身の満足度を高め、ストレス軽減や健康維持にも大きく役立ちます。
今回紹介した「素材別の捨て方」「トイレに流す際の注意点」「臭わせないコツ」を実践すれば、もう猫砂の処分方法に迷うことはありません。
フローチャートや早見表を参考に、ご自身の状況に合った最適な方法を見つけてください。
正しい知識を身につけ、日々のトイレ掃除をストレスフリーなものに変えていきましょう。
それが、飼い主さんと大切な愛猫の双方にとって、より豊かで素晴らしい関係を築くための一歩となるはずです。
大切なペットの移動にはペットタクシー「かるたく」がおすすめ

ペットタクシー「かるたく」は、愛玩動物飼養管理士の資格を持つドライバーが、大切なペットを安心・安全に送迎するサービスです。
動物病院への送迎が全体の55.9%を占め、ペットの体調に配慮した運転を心掛けています。料金は事前にシミュレーションでき、明瞭な価格設定が魅力です。車内は広々としており、多頭飼いの方も安心。
ペット用ラグジュアリークッションやスロープを完備し、快適な移動をサポートします。さらに、乗車毎の除菌・清掃・消臭を徹底し、清潔な環境を提供。
ペットホテル、引っ越し、トリミング、旅行など、さまざまなシーンでご利用いただけます。今なら最大50%オフのキャンペーン実施中。大切なペットとの移動に、ぜひ「かるたく」をご利用ください。