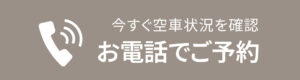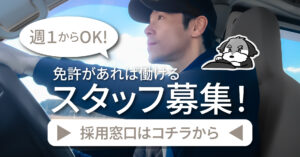愛猫がしきりに自分の爪を噛む姿を見て、「何か痛いのかな?」「もしかしてストレス?」と心配になっていませんか。猫が爪を噛む行動には、単なるお手入れの場合もあれば、病気やストレスが隠れている危険なサインの可能性もあります。この記事では、猫の爪噛みの原因を徹底解説。心配ないケースとの見分け方から、家庭でできる具体的な対処法、動物病院へ行くべき危険なサインまで、あなたの不安を解消するための情報を網羅しています。愛猫の小さな変化に気づき、健やかな毎日を守るための知識を身につけましょう。
まずは結論!猫の爪噛みは「心配ないケース」と「危険なケース」がある

猫が爪を噛む行動には、大きく分けて2つの側面があります。多くの場合は、猫自身の習性による生理現象であり、心配する必要はありません。
これは、人間が爪を切ったり爪の間の汚れを取ったりするのと同じ、ごく自然なお手入れ行動の一環です。
しかし、その一方で、特定の爪だけを執拗に噛み続けたり、出血や腫れが見られたりする場合は注意が必要です。その行動の裏には、ストレスや不安、さらにはケガや病気といった見過ごせない原因が隠れている可能性があります。
愛猫の行動がどちらのケースに当てはまるのか、その見分け方と原因別の正しい対処法を知ることが、猫の健康を守るための第一歩となるでしょう。
心配いらない!猫の習性による正常な爪噛みの2つの理由

猫の爪噛み行動のほとんどは、猫が元来持っている習性によるものです。そのため、過度に心配する必要はないケースがほとんどです。
これから解説する2つの理由は、猫が健康な体を維持するために行う、ごく自然な行動です。愛猫の様子と照らし合わせながら、まずは安心できる理由から確認していきましょう。
①グルーミング(お手入れ)の一環
猫が爪を噛む最も一般的な理由は、グルーミングの一環です。グルーミングとは、猫が自分の体や被毛を舐めて清潔に保つ「毛づくろい」行動全般を指します。
猫は非常にきれい好きな動物であり、体の隅々まで丁寧にお手入れする習性があります。その一環として、爪の間に挟まったゴミや汚れを、歯を使って器用に取り除いているのです。
まるで人間が爪楊枝で歯の掃除をするかのように、猫は自分の歯と舌を使い、爪を常に衛生的な状態に保っています。特に、排泄後に猫砂をかいた後などによく見られる行動です。
他の異常が見られなければ、これは健康的な行動と言えるでしょう。
②爪の脱皮(古い爪の除去)
猫の爪噛みには、爪のメンテナンスという重要な役割もあります。猫の爪は玉ねぎのように何層にもなっており、外側の古い爪が剥がれて新しい鋭い爪が現れる「爪の脱皮」をします。
爪とぎによってある程度は自然に剥がれ落ちますが、うまく剥がれなかったり、剥がれかけて気になったりする古い爪の層を、猫は自分で噛んで取り除くことがあります。
これは、常に鋭い爪を維持するための大切な習性です。爪切りを定期的に行っていても、この行動は見られます。
爪とぎの後に噛んでいる様子や、床に剥がれ落ちた爪のかけらが見つかる場合は、この爪の脱皮が理由である可能性が高いでしょう。
もしかして病気?注意すべき危険な爪噛みの5つの原因

一方で、猫の爪噛みが単なる習性ではない、危険なサインである場合もあります。ストレスやケガ、病気などが原因で、不快感や痛みから爪を噛んでしまうケースです。
これから紹介する5つの原因は、飼い主さんが注意深く観察し、場合によっては適切な対処が必要になります。愛猫の行動に隠されたSOSを見逃さないようにしましょう。
①ストレス・不安・退屈による常同行動
猫は環境の変化に敏感な生き物であり、ストレスが原因で爪を噛むことがあります。この行動は「常同行動」と呼ばれ、不安や葛藤を解消するために、特定の行動を執拗に繰り返す状態を指します。
例えば、引っ越しや家族構成の変化、長時間の留守番、運動不足による退屈などが、猫にとって大きなストレス要因となります。自分の気持ちを落ち着かせるために、爪を噛むという行為に没頭してしまうのです。
過剰なグルーミングで毛が禿げてしまう「舐性皮膚炎」と同様に、爪噛みがエスカレートすると自傷行為につながる恐れもあります。
爪以外にも落ち着きがない、食欲不振などの変化が見られる場合は、ストレスを疑いましょう。
②爪の伸びすぎや巻き爪などのトラブル
爪自体の物理的な問題が、猫を爪噛みに向かわせることもあります。特に、爪が伸びすぎるとカーペットに引っかかりやすくなったり、ひどい場合は肉球に食い込んで痛みを生じさせたりします(巻き爪)。
高齢の猫は爪とぎの頻度が減り、爪が太く硬くなるため、伸びすぎや巻き爪のリスクが高まります。若くても、爪とぎの場所が気に入らない、爪切りの習慣がないなどの理由で爪が伸びすぎてしまうことがあります。
猫はこれらの違和感や痛みを取り除こうとして、問題のある爪を必死に噛もうとします。
特定の足をしきりに気にしている様子が見られたら、一度爪の状態を確認してあげることが重要です。
③爪の割れ・ケガ・異物が刺さっている
人間と同じように、猫も爪を割ってしまったり、指先にケガをしたりすることがあります。高い場所からの着地の失敗、ドアに指を挟むなどの事故で爪が根元から折れたり、割れたりすると、強い痛みを伴います。
また、散歩に出る猫の場合、屋外でガラス片や植物のトゲなどが肉球や指の間に刺さってしまうことも考えられます。室内飼いの猫でも、床に落ちている小さな異物を踏んでしまう危険性があります。
猫は痛みや違和感の原因となっているものを取り除こうとして、患部を執拗に噛んだり舐めたりします。
歩き方がおかしい、特定の足を触られるのを嫌がるといったサインが見られたら、ケガの可能性を疑いましょう。
④皮膚病やアレルギーによるかゆみ・痛み
指先や爪の周りに、病気が原因でかゆみや痛みが発生している可能性も考えられます。アトピー性皮膚炎や食物アレルギー、ノミやダニのアレルギーなどが原因で、指先に強い炎症とかゆみが生じ、それを紛らわすために爪を噛む行動が見られます。
アレルギーの場合、指先だけでなく、顔や耳、お腹など他の部位にもかゆみや脱毛といった症状が出ることが多いです。
また、細菌や真菌の感染によって指の間が化膿し、痛みや不快感から患部を気にして噛み続けることもあります。
爪噛みと同時に、皮膚の赤みやフケ、脱毛などが見られる場合は、皮膚疾患を疑い、獣医師の診察を受けることをお勧めします。
⑤感染症など病気の可能性
頻度は低いものの、全身性の病気が爪の症状として現れることもあります。例えば、猫免疫不全ウイルス感染症(猫エイズ)や猫白血病ウイルス感染症などの影響で免疫力が低下し、爪の周りで細菌感染が起こりやすくなることがあります。
また、「狼瘡様爪床炎(ろうそうようそうしょうえん)」のような自己免疫疾患が原因で、爪が脱落したり変形したりして、痛みを伴うケースも報告されています。
これらの病気が原因の場合、爪噛み以外にも食欲不振、体重減少、発熱、口内炎といった全身的な症状が見られることが一般的です。
爪の異常に加えて、猫の元気や食欲にも変化が見られる場合は、早急に動物病院を受診する必要があります。
すぐに動物病院へ!受診を判断するべき危険なサイン【チェックリスト】

愛猫の爪噛みが「心配ない習性」なのか、それとも「危険なサイン」なのかを判断するのは難しいものです。しかし、いくつかのポイントを注意深く観察することで、動物病院へ行くべきかどうかの目安になります。
以下のチェックリストを参考に、愛猫の爪、指、そして全身の様子を改めて確認してみてください。一つでも当てはまる場合は、獣医師への相談を強く推奨します。
【爪・指の異常】こんな症状はありませんか?
まずは、猫が噛んでいる爪や指そのものに異常がないかを確認しましょう。物理的な問題や炎症が起きている場合、見た目や行動に明らかな変化が現れます。これらのサインは、猫が痛みや不快感を抱えている証拠です。
特定の指や爪だけを執拗に噛む・舐める
グルーミングであれば、前足や後ろ足の爪をまんべんなく手入れします。しかし、一本の指や特定の爪だけを、時間を忘れたように執拗に噛み続けたり、ずっと舐めていたりする場合は注意が必要です。
その指に爪の割れやケガ、巻き爪、異物が刺さっているなど、何らかの局所的なトラブルが起きている可能性が高いサインです。猫はその違和感を取り除こうと、集中的にその場所を気にします。
また、ストレスが原因の場合も、同じ場所を噛み続けることで常同行動に陥っていることが考えられます。どちらにせよ、自然なグルーミングの範囲を超えた行動と言えるでしょう。
爪の根元が赤く腫れている・出血や膿が出ている
爪や指の状態を直接確認し、炎症のサインがないかを見てください。爪の生え際やまわりの皮膚が赤く腫れている、触ると熱を持っている、出血している、または黄色や緑色の膿が出ているといった症状は、細菌感染を起こしている明らかな証拠です。
巻き爪が肉球に食い込んで化膿しているケースや、ケガをした傷口から細菌が入り込んでしまったケースなどが考えられます。
このような状態を放置すると、感染が骨にまで達するなど、より深刻な事態に進行する恐れがあります。痛みも相当なものであるため、家庭での対処は困難です。
速やかに動物病院で適切な処置を受ける必要があります。
爪がボロボロ、変色している
健康な猫の爪は、半透明で滑らかな表面をしています。もし爪が乾燥してボロボロと崩れる、層が異常に剥がれる、色が黒や黄色などに変色している、といった変化が見られる場合は、真菌(カビ)の感染や栄養障害、何らかの全身性疾患の可能性が疑われます。
特に、爪の変形や変色は、体に潜む病気のサインであることが少なくありません。爪は健康のバロメーターとも言われる部分です。
単なる爪のトラブルと軽視せず、爪の質自体に異常を感じた場合は、一度獣医師に相談し、原因を調べてもらうことが大切です。病気の早期発見につながる可能性もあります。
【行動・様子の異常】こんな変化はありませんか?
爪や指だけでなく、猫の全身の動きや様子にも注意を払いましょう。痛みや体調不良は、歩き方や普段の行動にも現れます。これらのサインは、猫が体全体で不調を訴えている重要なメッセージです。
足を引きずる・かばうように歩く
猫が痛みを感じている場合、その足をかばうような行動をとります。歩くときに特定の足を引きずったり、着地させずに浮かせて歩いたり(跛行:はこう)、高い場所に上るのをためらったりする様子が見られたら、その足に強い痛みがあると考えられます。
爪のトラブルはもちろん、骨折や捻挫、関節炎といった他のケガや病気の可能性も視野に入れる必要があります。
猫は不調を隠すのが得意な動物ですが、歩き方の異常は隠しきれない痛みのサインです。このような行動が見られた場合は、無理に動かさず、安静にさせた状態で動物病院へ連れて行きましょう。
触られるのを極端に嫌がる
普段は触らせてくれる場所を、急に嫌がるようになるのも注意すべき変化です。気にしている足を飼い主が触ろうとしたときに、唸ったり、噛みついたり、悲鳴をあげて逃げたりするのは、そこに触れられたくないほどの痛みがある証拠です。
猫は信頼している飼い主に対してでさえ、痛みがある場所を触られることには非常に敏感に反応します。
無理に触って状態を確認しようとすると、猫にさらなる苦痛を与え、飼い主自身がケガをする危険性もあります。どこを痛がっているのかを特定するためにも、専門家である獣医師に診てもらうのが最も安全で確実な方法です。
食欲不振や元気消失など他の症状がある
爪噛みという一つの症状だけでなく、猫の全体的な健康状態を見ることが非常に重要です。爪を噛む行動とあわせて、食欲がない、水を飲まない、遊ばなくなった、ぐったりしている、嘔吐や下痢をしているなど、他の体調不良のサインが見られる場合は、何らかの全身的な病気が隠れている可能性があります。
前述したウイルス感染症や自己免疫疾患、アレルギーなど、体の内部に原因がある場合、爪の異常は数ある症状の一つに過ぎません。
体調全般が悪化しているサインを見逃さず、複数の症状が見られる場合は、緊急性が高いと判断して、できるだけ早く動物病院を受診してください。
今日からできる!飼い主ができる原因別の対処法

愛猫の爪噛みの原因が、病気やケガではなく、爪のケア不足やストレスにある場合、ご家庭での対策によって改善できることがあります。もちろん、危険なサインが見られる場合は動物病院へ行くことが最優先です。
ここでは、飼い主さんが今日から実践できる具体的な対処法を3つの観点からご紹介します。
【爪のケア】正しい爪切りの頻度と方法
爪の伸びすぎや巻き爪を防ぐためには、定期的な爪切りが最も効果的です。猫の爪切りの頻度は、活動量や年齢にもよりますが、一般的には2週間から1ヶ月に1回が目安です。
猫用の爪切りを用意し、一度にすべての爪を切ろうとせず、猫がリラックスしている時に1本ずつでも良いので挑戦してみましょう。爪のピンク色の部分(血管が通っている部分)を避け、先端の尖った部分だけを切るのがコツです。
どうしても嫌がる場合や、爪が黒くて血管が見えにくい場合は、無理をせず動物病院やペットサロンにお願いするのも良い選択です。正しい爪のケアは、トラブルを未然に防ぐ基本となります。
【ストレスの軽減】遊びや環境を見直して安心できる暮らしを
ストレスが原因で爪を噛んでいると考えられる場合、猫が安心して快適に過ごせる環境を整えることが重要です。特に、猫の狩猟本能を満たすような遊びの時間を毎日設けることは、ストレスや退屈の解消に非常に効果的です。
猫じゃらしやボールなどのおもちゃを使って、1日に5分から10分程度の遊びを2回ほど行い、エネルギーを発散させてあげましょう。
また、爪とぎ器を複数設置する、上下運動ができるキャットタワーを用意する、窓の外が見える場所を作るなど、猫が退屈しない環境作りも大切です。愛猫とのコミュニケーションを増やし、安心感を与えてあげることが、問題行動の改善につながります。
【病気・ケガが疑われる場合】自己判断せず動物病院へ相談を
ここまで家庭でできる対処法を紹介しましたが、最も重要なことをお伝えします。愛猫の爪噛みに少しでも異常を感じたり、原因がわからなかったりした場合は、決して自己判断せず、速やかに獣医師に相談してください。
特に、出血や腫れ、歩行異常などの危険なサインが見られる場合は、一刻も早い受診が必要です。インターネットの情報だけで判断したり、人間用の薬を使ったりすることは、症状を悪化させる危険性が高く非常に危険です。
専門家である獣医師に正確な診断をしてもらい、適切な治療を受けることが、愛猫を苦痛から救うための最善の方法です。不安な時は、ためらわずにプロの力を頼りましょう。
猫の爪噛みに関するよくある質問
ここでは、猫の爪噛みに関して飼い主さんからよく寄せられる質問とその回答をQ&A形式でまとめました。愛猫の行動についてさらに深く理解し、日々のケアに役立ててください。
Q. 子猫や老猫が爪を噛むのは特に注意が必要ですか?
はい、注意が必要です。子猫の場合、好奇心や遊びの一環で爪を噛むこともありますが、成猫より爪が柔らかく、ケガにつながりやすい側面もあります。
一方、老猫(シニア猫)の場合は、活動量の低下や関節の痛みから爪とぎの頻度が減り、爪が伸びすぎて巻き爪になりやすい傾向にあります。
また、認知機能の低下によって常同行動として爪を噛み続けることも考えられます。子猫、老猫ともに、成猫以上にこまめな爪のチェックとケアが必要です。特に老猫は体調の変化に気づきにくいこともあるため、注意深く観察してあげましょう。
Q. 爪噛みをやめさせる市販のグッズ(苦いスプレーなど)は効果がありますか?
爪噛み防止用の苦い味のするスプレーなどが市販されていますが、その使用には慎重な判断が求められます。メリットとしては、スプレーの苦みによって物理的に噛む行為を止めさせられる可能性がある点です。
しかし、デメリットとして、根本的な原因(ストレスや病気など)が解決されない限り、別の場所を噛んだり、他の問題行動に移ったりする可能性があります。
また、猫がグルーミングを嫌がるようになり、ストレスを増大させる危険性も否定できません。これらのグッズを使用する前に、まずは爪噛みの原因を特定し、その原因を取り除くアプローチを優先すべきです。
Q. ストレスが原因の場合、どんな遊びが効果的ですか?
ストレスが原因の場合、猫の狩猟本能を刺激する遊びが非常に効果的です。猫じゃらしやレーザーポインターなどを使い、獲物に見立てた動きで猫の興味を引き、「捕まえる」という達成感を与えてあげることがポイントです。
遊びの終わりには、おもちゃを「捕まえさせて」満足感を与えることが重要です。レーザーポインターの場合は実体がないため、最後はおやつを与えるなどして狩りを完了させてあげましょう。
このようなメリハリのある遊びは、運動不足の解消だけでなく、精神的な満足感ももたらし、ストレス軽減に大きく貢献します。毎日の習慣として取り入れることをお勧めします。
Q. 多頭飼いの場合、他の猫との関係もストレスになりますか?
はい、多頭飼いの環境では、他の猫との関係が大きなストレス要因になることがあります。猫は縄張り意識が強い動物なので、相性が悪い猫との同居、新入り猫の存在、食事場所やトイレの共有などがストレスを引き起こす可能性があります。
他の猫に威嚇されたり、自分の居場所がなかったりすると、猫は不安を感じて爪噛みなどの常同行動に走りやすくなります。
各猫が安心して過ごせるプライベートな空間(隠れ家)を用意する、食事やトイレは猫の数+1個を基本に設置するなど、縄張りに配慮した環境作りが重要です。猫同士の関係性を注意深く観察し、ストレスのサインを見逃さないようにしましょう。
まとめ:日々の観察が愛猫の健康を守る鍵。不安な時は迷わず獣医師に相談を

この記事では、猫が爪を噛む行動について、心配のいらない生理的な理由から、注意すべき病気やストレスのサインまでを詳しく解説しました。猫の爪噛みは、多くがグルーミングなどの自然な習性ですが、時には愛猫が送る健康上のSOSである可能性も秘めています。
最も大切なのは、飼い主であるあなたが、普段から愛猫の様子をよく観察し、小さな変化に気づいてあげることです。「いつもと違うな」と感じたら、本記事のチェックリストを参考に、爪や体の状態を確認してみてください。
そして、少しでも不安や疑問があれば、決して一人で抱え込まず、信頼できる獣医師に相談することが、愛猫の健康と幸せな毎日を守るための最も確実な方法です。日々のコミュニケーションを通じて、愛猫の健やかな暮らしをサポートしていきましょう。
大切なペットの移動にはペットタクシー「かるたく」がおすすめ

ペットタクシー「かるたく」は、愛玩動物飼養管理士の資格を持つドライバーが、大切なペットを安心・安全に送迎するサービスです。
動物病院への送迎が全体の55.9%を占め、ペットの体調に配慮した運転を心掛けています。料金は事前にシミュレーションでき、明瞭な価格設定が魅力です。車内は広々としており、多頭飼いの方も安心。
ペット用ラグジュアリークッションやスロープを完備し、快適な移動をサポートします。さらに、乗車毎の除菌・清掃・消臭を徹底し、清潔な環境を提供。
ペットホテル、引っ越し、トリミング、旅行など、さまざまなシーンでご利用いただけます。今なら最大50%オフのキャンペーン実施中。大切なペットとの移動に、ぜひ「かるたく」をご利用ください。