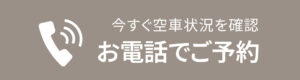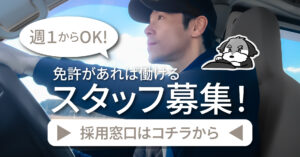愛犬の抜け毛、あまりの量に「もしかして病気?」と不安になったり、掃除の大変さにうんざりしたりしていませんか。犬の抜け毛には、心配いらない生理現象から注意すべき病気のサインまで様々な原因があります。
この記事では、犬の抜け毛の主な原因から、今日からすぐに実践できる犬種別の効果的な対策、さらには大変な掃除を楽にするコツまで、飼い主さんの悩みを解決する情報を網羅的に解説します。正しい知識を身につけ、抜け毛と上手に付き合いながら、愛犬との快適な毎日を送りましょう。
まずは結論!犬の抜け毛の主な原因と対策が一目でわかる比較表

犬の抜け毛に関する悩みは多岐にわたりますが、まずは原因と対策の全体像を把握することが大切です。ここでは、主な原因とそれに対応する基本的な対策を一覧表にまとめました。
愛犬の抜け毛がどのケースに当てはまるかを確認し、適切なケアを始めるための参考にしてください。それぞれの詳細については、この後の見出しで詳しく解説していきます。
| 主な原因 | 状態 | 基本的な対策 |
|---|---|---|
| 生理現象(換毛期) | 春と秋に毛が大量に抜ける。全身から均一に抜ける。 | こまめなブラッシング、定期的なシャンプー |
| 病気の可能性 | 特定の場所だけ抜ける、皮膚に赤みやかゆみがある。 | すぐに動物病院を受診する |
| 食事・栄養の偏り | 毛艶がなくパサパサしている、毛が切れやすい。 | バランスの取れたフードへの見直し、サプリメントの活用 |
| ストレスや不適切なケア | 体を頻繁にかく、舐める。フケが多い。 | ストレス原因の除去、正しいブラッシングやシャンプーの実践 |
なぜ抜ける?犬の抜け毛、考えられる4つの主な原因

愛犬の抜け毛がなぜ起こるのか、その背景にはいくつかの理由が考えられます。季節的なものから、健康状態を示すサインまで様々です。ここでは、犬の抜け毛を引き起こす代表的な4つの原因を掘り下げて解説します。原因を正しく理解することが、効果的な対策への第一歩となります。
①【生理現象】換毛期による自然な抜け毛
犬の抜け毛の最も一般的な原因は、換毛期(かんもうき)と呼ばれる生理現象です。 これは、季節の変化に対応するために被毛が生え変わる自然なサイクルであり、病気ではありません。
換毛期とは、古い毛が抜け落ちて新しい毛が生えてくる期間を指します。人間でいう衣替えのようなもので、特に気温の変化が激しい春と秋に多くの毛が抜ける傾向にあります。この時期の抜け毛は、愛犬が健康に季節を乗り越えるための準備をしている証拠なので、過度に心配する必要はありません。
ダブルコートの犬種は特に抜け毛が多くなる
犬の被毛には、大きく分けて「ダブルコート」と「シングルコート」の2種類があります。特に抜け毛が多くなるのは、ダブルコートの犬種です。
ダブルコートとは、皮膚を保護する硬めの「オーバーコート(上毛)」と、体温を調節する柔らかい「アンダーコート(下毛)」の二層構造になっている被毛のことです。柴犬やゴールデン・レトリバーなどが代表的で、換毛期には主にこのアンダーコートがごっそりと抜け落ちるため、抜け毛の量が非常に多くなります。
換毛期の時期は春と秋の年2回
犬の換毛期は、主に春と秋の年に2回訪れます。 春には、冬の寒さから体を守っていた密度の高い冬毛(アンダーコート)が抜け落ち、夏に向けて通気性の良い夏毛に生え変わります。
そして秋には、夏毛が抜けて、これから来る冬の寒さに備えるための保温性の高い冬毛が生えてきます。このサイクルは日照時間や気温の変化によって起こるため、室内飼育で一年中快適な温度で暮らしている犬の場合、換毛期の時期がずれたり、一年を通して少しずつ毛が抜け続けたりすることもあります。
②【病気のサインかも】注意すべき危険な抜け毛・脱毛の症状
すべての抜け毛が自然現象とは限りません。部分的にごそっと毛が抜ける、皮膚に赤みやかゆみが見られるといった症状は、病気のサインである可能性があります。
換毛期のように全身から均一に抜けるのではなく、体の一部分だけが脱毛していたり、フケが異常に多かったりする場合は注意が必要です。愛犬の体を撫ぜながら、皮膚の状態も一緒にチェックする習慣をつけましょう。いつもと違う様子に気づいたら、早めに専門家へ相談することが重要です。
アレルギー性皮膚炎や膿皮症などの皮膚病
犬の脱毛を引き起こす代表的な病気に、アレルギー性皮膚炎や膿皮症(のうひしょう)などがあります。 アレルギー性皮膚炎は、食べ物やハウスダストなどが原因で皮膚に炎症が起こり、強いかゆみから体をかきむしって毛が抜けてしまう病気です。
一方、膿皮症は皮膚のバリア機能が低下し、ブドウ球菌などの細菌に感染して起こる皮膚病です。赤い発疹や膿(うみ)がたまった水疱ができ、脱毛を伴うことがあります。これらの病気は、適切な治療が必要となるため、自己判断せずに獣医師の診察を受けましょう。
甲状腺機能低下症などの内分泌系の病気
皮膚病以外にも、体の内側にある病気が抜け毛の原因となることがあります。特に中高齢の犬に多いのが、甲状腺機能低下症(こうじょうせんきのうていかしょう)などの内分泌系の病気です。
甲状腺機能低下症とは、体の新陳代謝を活発にする甲状腺ホルモンの分泌が減少する病気です。症状の一つとして、体の左右対称に毛が薄くなる「対称性脱毛」が見られるのが特徴です。かゆみは伴わないことが多く、「なんとなく元気がない」「太りやすくなった」といった他の症状が見られる場合は、この病気を疑う必要があります。
部分的な脱毛や皮膚の赤み、かゆみは病院へ
愛犬に部分的な脱毛や皮膚の赤み、強いかゆみ、フケなどの症状が見られたら、すぐに動物病院を受診してください。 これらは、皮膚病や内分泌系の病気、あるいはノミ・ダニなどの寄생충が原因である可能性を示す重要なサインです。
特に、犬が同じ場所を執拗に舐めたり噛んだりしている場合は、痛みやかゆみを感じている証拠です。病気の早期発見・早期治療は、愛犬の負担を軽減する上で非常に重要です。様子を見るのではなく、まずは獣医師に相談し、正確な診断を受けることを強く推奨します。
③【食事・栄養】フードが合っていない可能性
毎日の食事が、愛犬の被毛の健康状態に大きく影響していることがあります。 毛の主成分はタンパク質であるため、質の良いタンパク質が不足すると、毛が細くなったり、抜けやすくなったりします。
また、皮膚や被毛の健康を維持するためには、オメガ3脂肪酸やオメガ6脂肪酸、亜鉛、ビタミン類などの栄養素も欠かせません。もし、愛犬の毛艶が悪かったり、フケが多かったりする場合は、現在与えているドッグフードの成分を見直してみるのも一つの手です。栄養バランスの取れた食事が、健康な被毛作りの基本となります。
④【その他】ストレスや老化、不適切なケア
病気や栄養不足以外にも、抜け毛の原因は存在します。引っ越しなどの環境の変化や、飼い主とのコミュニケーション不足によるストレスが、抜け毛を引き起こすことがあります。
犬はストレスを感じると、体を舐め続ける「舐性皮膚炎(しせいひふえん)」などを発症し、その部分の毛が抜けてしまうことがあります。また、シニア犬になると新陳代謝が衰え、毛の生え変わるサイクルが乱れて抜け毛が増えることもあります。さらに、洗浄力の強すぎるシャンプーや、間違ったブラッシングが皮膚を傷つけ、抜け毛を悪化させているケースも考えられます。
【今日からできる】シーン別・犬の抜け毛対策7選

抜け毛の原因を理解したところで、次は具体的な対策について見ていきましょう。日々の少しの工夫で、抜け毛の悩みは大きく軽減できます。ここでは、毎日のケアから住環境の見直しまで、今日からすぐに始められる7つの効果的な対策をご紹介します。
①基本のケア:正しいブラッシングの方法と頻度
抜け毛対策の基本中の基本は、こまめなブラッシングです。 ブラッシングには、抜け落ちる前の毛を取り除き、部屋に毛が散らばるのを防ぐ効果があります。
さらに、皮膚の血行を促進して健康な毛の成長を助けたり、飼い主とのスキンシップの時間になったりというメリットもあります。換毛期には毎日、それ以外の時期でも週に2〜3回行うのが理想です。毛の流れに沿って優しくとかし、毛が絡まっている部分は無理に引っ張らず、丁寧にもつれをほどいてあげましょう。
犬種に合ったブラシ(スリッカー、コーム等)の選び方
ブラッシングの効果を最大限に引き出すには、愛犬の毛質に合ったブラシを選ぶことが重要です。代表的なブラシには、スリッカーブラシやコーム、ラバーブラシなどがあります。
スリッカーブラシは「く」の字に曲がった細いピンがたくさん付いており、ダブルコートの犬種のアンダーコートを取り除くのに最適です。一方、コームは毛並みを整えたり、毛玉がないか最終チェックをしたりするのに使います。皮膚がデリケートな短毛種には、柔らかい素材でできたラバーブラシがマッサージ効果もあっておすすめです。
②皮膚を清潔に:効果的なシャンプーのやり方と注意点
定期的なシャンプーは、抜け毛やフケ、汚れを洗い流し、皮膚を清潔に保つために非常に効果的です。 ただし、シャンプーのしすぎは逆効果になることもあります。
シャンプーの頻度は、月に1〜2回が目安です。洗いすぎると、皮膚を守るために必要な皮脂まで落としてしまい、乾燥や皮膚トラブルの原因になります。シャンプーをする際は、犬用の製品を使い、ぬるま湯で全身をしっかりと濡らしてから、よく泡立てて優しくマッサージするように洗いましょう。すすぎ残しはかゆみの原因になるため、シャワーで丁寧に洗い流してください。
③体の中からケア:被毛の健康をサポートする食事・栄養素
健康で丈夫な被毛を育むためには、バランスの取れた食事が不可欠です。 特に、良質なタンパク質は被毛の主成分であり、最も重要な栄養素と言えます。
ドッグフードを選ぶ際は、主原料に質の良い肉や魚が使われているものを選びましょう。また、皮膚の健康維持に役立つ「オメガ3脂肪酸」や「オメガ6脂肪酸」、被毛の色艶を保つ「亜鉛」なども積極的に摂取したい栄養素です。必要に応じて、これらの栄養素が含まれたサプリメントを食事にプラスするのも良いでしょう。
④プロにお任せ:トリミングサロンの活用法
自宅でのケアに限界を感じたら、プロの力を借りるのも賢い選択です。 トリミングサロンでは、シャンプーやカットだけでなく、抜け毛対策に特化したサービスを提供しているところも多くあります。
例えば、マイクロバブルバスやハーブパックなどは、毛穴の奥の汚れまでしっかり落とし、抜け毛をすっきりと除去する効果が期待できます。また、プロのトリマーは、その犬の毛質や皮膚の状態に合った最適なケア方法を熟知しています。定期的にサロンを利用することで、家庭での抜け毛管理が格段に楽になります。
⑤飛び散り防止:犬用の服を着せるメリット・デメリット
犬に服を着せることは、部屋の中に毛が飛び散るのを防ぐという点で、非常に手軽で効果的な対策です。 特に、来客時や公共の場へ出かける際に役立ちます。
ただし、服を着せることにはデメリットも存在します。長時間の着用は、服と被毛がこすれて毛玉ができやすくなったり、皮膚が蒸れて皮膚炎の原因になったりすることがあります。服を着せる場合は、通気性の良い素材を選び、こまめにブラッシングをして毛玉ができないように注意しましょう。あくまで一時的な対策と考えるのが良いでしょう。
⑥住環境の見直し:湿度管理とストレス軽減
快適な生活環境を整えることも、間接的な抜け毛対策につながります。 特に、空気の乾燥は皮膚の乾燥を招き、フケやかゆみ、抜け毛を悪化させる原因となります。
冬場など乾燥しやすい季節には、加湿器を使用して適切な湿度(50〜60%程度)を保つように心がけましょう。また、犬が安心して過ごせる静かな寝床を用意したり、十分な運動や遊びの時間を確保したりして、ストレスを溜めさせない工夫も大切です。飼い主とのポジティブな関わりが、愛犬の心と体の健康を支えます。
⑦病院での相談:動物病院を受診するタイミングの判断基準
もし抜け毛以外に気になる症状が見られたら、迷わず動物病院を受診してください。 判断基準としては、「体の一部だけがハゲている」「皮膚が赤い」「体をかきむしっている」「フケが異常に多い」などが挙げられます。
これらの症状は、何らかの病気が隠れているサインかもしれません。獣医師は、皮膚検査や血液検査などを用いて原因を正確に診断し、適切な治療法を提案してくれます。特に換毛期でもないのに抜け毛がひどい場合や、急に抜け毛が増えた場合も、一度相談してみることをおすすめします。
【犬種で違う?】抜け毛が多い犬・少ない犬の特徴

犬の抜け毛の量は、犬種によって大きく異なります。これは、それぞれの犬種が持つ被毛の構造、つまり「コートタイプ」が違うためです。ここでは、抜け毛が多い犬種と少ない犬種の特徴について解説します。これから犬を迎えようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
抜け毛が多い「ダブルコート」の代表的な犬種
抜け毛が多いとされるのは、主に「ダブルコート」と呼ばれる二層構造の被毛を持つ犬種です。 前述の通り、このタイプの犬は季節の変わり目にアンダーコートが大量に抜ける「換毛期」があります。
日本の気候に適応してきた日本犬や、寒い地域が原産の犬種に多く見られます。日々のブラッシングが欠かせませんが、フワフワとした豊かな被毛が魅力でもあります。
- 柴犬
- ゴールデン・レトリバー
- シベリアン・ハスキー
- ウェルシュ・コーギー・ペンブローク
- ポメラニアン
抜け毛が少ない「シングルコート」の代表的な犬種
一方で、抜け毛が少ないとされるのは「シングルコート」の被毛を持つ犬種です。 このタイプの犬は、アンダーコートがなく、オーバーコートのみで被毛が構成されています。
そのため、換毛期がなく、抜け毛の量が比較的少ないのが特徴です。ただし、人間の髪の毛と同じように毛は伸び続けるため、定期的なカット(トリミング)が必要な犬種が多く含まれます。
- トイ・プードル
- ミニチュア・シュナウザー
- マルチーズ
- シーズー
- ヨークシャー・テリア
抜け毛が少ない犬種でも毎日のケアは必要
抜け毛が少ないとされるシングルコートの犬種でも、ブラッシングなどの日々のお手入れが不要というわけではありません。 抜け毛は少なくても、毛が伸び続ける犬種は毛が絡まりやすく、毛玉ができやすい傾向にあります。
毛玉を放置すると、皮膚が引っ張られて痛みが出たり、通気性が悪くなって皮膚炎の原因になったりします。そのため、シングルコートの犬種であっても、毛玉を防ぎ、皮膚の健康を保つために、毎日のブラッシングは非常に重要です。
もう悩まない!場所・モノ別の抜け毛お掃除術&便利グッズ

どれだけ対策をしても、犬と暮らす以上、抜け毛をゼロにすることはできません。しかし、掃除のコツを知っていれば、その負担を大きく減らすことができます。ここでは、悩まされがちな場所やモノ別に、効率的な掃除方法と便利なグッズをご紹介します。
フローリング・床はペーパーモップが効果的
フローリングに散らばった軽い抜け毛には、掃除機よりもドライタイプのペーパーモップが効率的です。 掃除機を使うと、排気で床の毛を舞い上げてしまい、かえって広げてしまうことがあります。
まずはペーパーモップで床全体の毛を静かに集めてから、取り切れなかったゴミを掃除機で吸う、という順番がおすすめです。特に、部屋の隅や家具の下には毛が溜まりやすいので、意識して掃除しましょう。日々の掃除には、この方法が手軽で効果的です。
カーペット・ラグはゴム手袋でこするのが裏ワザ
カーペットやラグに絡みついた抜け毛は、掃除機だけではなかなか取り切れません。そこでおすすめなのが、ゴム手袋を使う裏ワザです。
乾いたゴム手袋を手にはめ、カーペットの表面を一定方向に円を描くようにこするだけで、静電気の力で抜け毛が面白いように集まり、大きな毛玉になります。集まった毛玉を掃除機で吸い取れば完了です。特別な道具は必要なく、手軽に試せる非常に効果的な方法なので、ぜひ実践してみてください。
ソファ・衣類は粘着ローラーやエチケットブラシで
ソファやクッション、着ている洋服についてしまった抜け毛には、粘着式のカーペットクリーナー(通称コロコロ)やエチケットブラシが便利です。
粘着クリーナーは手軽に使えますが、布製品を傷めてしまう可能性もあるため、デリケートな素材には衣類用のエチケットブラシを使いましょう。エチケットブラシは、繰り返し使えて経済的というメリットもあります。車の中に持ち込んで、シートについた抜け毛を取るのにも重宝します。
掃除が楽になる!おすすめ便利グッズ(ロボット掃除機、ランドリースポンジなど)
日々の掃除の負担をさらに軽減してくれる便利なグッズもたくさんあります。 例えば、外出中や寝ている間に床掃除を自動で行ってくれるロボット掃除機は、犬を飼っている家庭の強い味方です。
また、洗濯の際に洗濯機に入れるだけで、衣類についた抜け毛を絡め取ってくれる「ランドリースポンジ」も人気です。これらのグッズをうまく活用することで、掃除にかかる時間と労力を大幅に削減し、愛犬との時間をもっと楽しむことができるようになります。
犬の抜け毛に関するよくある質問
ここでは、犬の抜け毛に関して飼い主さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。日々のケアや疑問の解消にお役立てください。
Q1. 換毛期はいつからいつまで続きますか?
A1. 一般的に、換毛期は春と秋にそれぞれ1ヶ月程度続くとされていますが、個体差や生活環境によって期間は大きく異なります。
室内で飼育され、一年を通して快適な温度で過ごしている犬の場合、明確な換毛期のピークがなく、一年中だらだらと毛が抜け続けることも珍しくありません。また、犬種や年齢によっても期間は変わってきます。通常よりも長く抜け毛が続く、あるいは他の症状が見られる場合は、獣医師に相談しましょう。
Q2. サマーカットは抜け毛対策に効果がありますか?
A2. 毛を短くカットするサマーカットは、抜けた毛が舞い散りにくくなるため、掃除は楽になります。しかし、抜け毛の量そのものを減らす効果はありません。
注意点として、ダブルコートの犬種(柴犬、コーギーなど)の被毛を短く刈りすぎると、毛質が変わってしまったり、生え揃わなくなったりすることがあります。また、被毛には直射日光から皮膚を守る役割もあるため、短くしすぎると皮膚トラブルや熱中症のリスクが高まる可能性も指摘されています。サマーカットを行う際は、トリマーとよく相談することが大切です。
Q3. 抜け毛を放置すると、犬や人にどんな影響がありますか?
A3. 抜け毛を放置すると、犬自身にも人間にも様々な悪影響を及ぼす可能性があります。
犬にとっては、抜けた毛が体に絡みついて毛玉となり、皮膚炎などのトラブルの原因になります。人間にとっては、抜け毛やフケがアレルギーの原因(アレルゲン)となり、くしゃみや喘息などのアレルギー症状を引き起こすことがあります。衛生的な環境を保つためにも、こまめな掃除とケアが重要です。
Q4. 抜け毛が少ない犬種はアレルギーが出にくいですか?
A4. 抜け毛が少ない犬種は、アレルゲンとなる毛やフケの飛散が少ないため、アレルギー症状が出にくい傾向にあると言えます。しかし、完全にアレルギーが出ないわけではありません。
犬アレルギーのアレルゲンは、毛そのものだけでなく、フケや唾液、尿などにも含まれています。そのため、抜け毛の少ない犬種であっても、アレルギー反応が起こる可能性は十分にあります。犬アレルギーの方が犬を飼う場合は、事前にアレルギー科の医師に相談したり、実際に犬と触れ合ってみたりすることをおすすめします。
まとめ:抜け毛は愛犬の健康のバロメーター。正しいケアで快適な毎日を
犬の抜け毛は、飼い主にとって悩みの種になりがちですが、その多くは換毛期という自然な生理現象です。 こまめなブラッシングや定期的なシャンプーといった日々の正しいケアを実践することで、抜け毛と上手に付き合っていくことができます。
一方で、抜け毛は愛犬の健康状態を知らせてくれる重要なバロメーターでもあります。部分的な脱毛や皮膚の異常など、いつもと違う様子に気づいたら、それは病気のサインかもしれません。迷わず動物病院を受診しましょう。
この記事でご紹介した原因や対策、掃除のコツを参考に、抜け毛への理解を深め、愛犬との暮らしをより快適で豊かなものにしてください。
大切なペットの移動にはペットタクシー「かるたく」がおすすめ

ペットタクシー「かるたく」は、愛玩動物飼養管理士の資格を持つドライバーが、大切なペットを安心・安全に送迎するサービスです。
動物病院への送迎が全体の55.9%を占め、ペットの体調に配慮した運転を心掛けています。料金は事前にシミュレーションでき、明瞭な価格設定が魅力です。車内は広々としており、多頭飼いの方も安心。
ペット用ラグジュアリークッションやスロープを完備し、快適な移動をサポートします。さらに、乗車毎の除菌・清掃・消臭を徹底し、清潔な環境を提供。
ペットホテル、引っ越し、トリミング、旅行など、さまざまなシーンでご利用いただけます。今なら最大50%オフのキャンペーン実施中。大切なペットとの移動に、ぜひ「かるたく」をご利用ください。