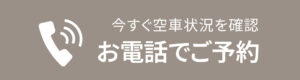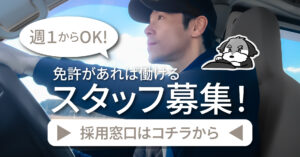愛犬の口の臭いが気になり、「犬の歯磨きの頻度はどれくらいが正解なの?」と疑問に思っていませんか。毎日が良いと聞くけれど、仕事で疲れていたり、愛犬が嫌がったりして、なかなか続けられないのが現実ですよね。この記事では、獣医師が推奨する理想的な歯磨きの頻度から、忙しい飼い主さんでも無理なく続けられる最低限の回数まで、具体的な理由と共に徹底解説します。さらに、歯磨きを嫌がる愛犬が好きになるためのステップや、正しい磨き方のコツもご紹介。この記事を読めば、あなたの愛犬に合ったデンタルケアが見つかり、口臭や歯周病の不安から解放されるはずです。
まずは結論!犬の歯磨きは「毎日」が理想、最低でも「3日に1回」

愛犬のデンタルケアについて、どれくらいの頻度で歯磨きをすれば良いのか、多くの飼い主さんが悩むポイントです。ここでは、なぜその頻度が必要なのか、そして愛犬の目的別に合わせた具体的な歯磨きの回数について、分かりやすく解説していきます。正しい知識を身につけて、効果的なデンタルケアを始めましょう。
なぜその頻度が必要?犬の歯垢が歯石に変わるスピード
結論として、犬の歯垢はわずか3〜5日で硬い歯石に変わってしまうため、毎日の歯磨きが理想とされています。
その理由は、犬の口内環境が人間と大きく異なるからです。犬の唾液はアルカリ性で、歯垢が歯石化しやすい性質を持っています。歯垢とは、歯の表面に付着した細菌の塊で、いわば「ネバネバした汚れ」のこと。この段階であれば、歯ブラシでこすれば簡単に取り除くことができます。
しかし、この歯垢を放置すると、唾液中のカルシウムなどと結びついて石のように硬い「歯石」へと変化します。歯石になってしまうと、家庭での歯磨きでは除去できず、動物病院で専門的な処置が必要になります。だからこそ、歯垢が歯石になる前の、3日以内にケアすることが最低限のラインとなるのです。
目的別!理想的な歯磨きの頻度が一目でわかる早見表
あなたの愛犬のお口の状態や、デンタルケアの目的に合わせて、歯磨きの頻度を設定することが大切です。
全ての犬に「毎日」が必須というわけではありませんが、理想を目指すことで、将来の病気のリスクを大きく減らすことができます。一方で、これまで全くケアをしてこなかった場合は、まず継続できる目標を立てることが成功の秘訣です。
以下の表を参考にして、ご自身の愛犬に合ったケアの頻度を見つけてみましょう。
| 目的 | 推奨される頻度 | 具体的な内容 |
|---|---|---|
| 病気の徹底予防(理想) | 毎日 | 歯周病を徹底的に予防し、常に清潔な口内環境を保ちたい場合に推奨されます。 |
| 健康な状態の維持(最低限) | 2〜3日に1回 | 歯垢が歯石に変わる前に除去し、現状の健康な状態を維持するための最低ラインです。 |
| 口臭や汚れが気になる | 毎日+補助ケア | すでに口臭や歯の汚れが見られる場合、毎日の歯磨きに加え、デンタルガムなどを併用します。 |
| 歯磨きに慣れさせる段階 | 毎日(短時間) | 歯磨き自体に慣れることが目標。全ての歯を磨けなくても、口に触れる練習を毎日行います。 |
まずは愛犬のお口をチェックし、どのレベルを目指すのかを決めることから始めてみてください。
歯磨きをしないとどうなる?放置が招く3つの怖いリスク

「うちの子は歯磨きを嫌がるし、少しぐらい大丈夫だろう」と考えてしまう気持ちも分かります。しかし、歯磨きをしないことのリスクは、単に口が臭くなるだけではありません。愛犬の健康寿命を縮めてしまう可能性のある、恐ろしい病気につながることもあるのです。ここでは、歯磨きを怠ることで引き起こされる3つの代表的なリスクを解説します。
リスク①:耐えられない口臭の発生
歯磨きをしないことで起こる最も分かりやすいサインが、強烈な口臭です。
この臭いの主な原因は、歯周病菌が作り出す「揮発性硫黄化合物」というガスによるものです。食べかすが歯と歯茎の間に溜まり、それをエサにして細菌が繁殖することで、腐敗臭のような不快な臭いが発生します。
最初は「少し魚臭いかな?」と感じる程度かもしれませんが、進行すると生ゴミやドブのような臭いに変化していくことも少なくありません。愛犬との楽しいコミュニケーションの時間も、口臭が原因でためらってしまうようになるのは悲しいことです。この口臭は、見た目以上に口内環境が悪化しているという、愛犬からの危険信号なのです。
リスク②:3歳以上の8割が発症する「歯周病」
実は、3歳以上の犬の約8割が歯周病にかかっていると言われており、歯磨きをしないことが最大の原因です。
歯周病とは、歯垢の中の細菌によって歯茎に炎症が起きる病気(歯肉炎)や、さらに進行して歯を支える骨まで溶かしてしまう病気(歯周炎)の総称です。初期段階では歯茎が赤く腫れる程度で、飼い主さんが気づきにくいのが特徴です。
しかし、症状が進行すると、歯がグラグラしたり、痛みのためにご飯が食べられなくなったり、硬いおもちゃで遊ばなくなったりします。最悪の場合、顎の骨が溶けて骨折したり、目の下に穴が開いて膿が出たりすることもあります。歯周病は一度進行すると元に戻すのが難しい、非常に厄介な病気なのです。
リスク③:心臓病など全身の病気につながる可能性
歯周病菌は口の中だけでなく、血管を通って全身に広がり、深刻な内臓疾患を引き起こす可能性があります。
口内の歯茎は血管が豊富で、炎症を起こした部分から歯周病菌が血液中に侵入しやすい状態になっています。血流に乗った細菌は、心臓や腎臓、肝臓といった重要な臓器にたどり着き、そこで新たな炎症を引き起こすことが研究で分かっています。
具体的には、心臓で炎症が起これば「心内膜炎」に、腎臓で起これば「腎臓病」につながるリスクが高まります。お口のケアを怠った結果が、命に関わる全身の病気につながってしまう可能性があるのです。愛犬の健康長寿のためにも、口内ケアは全身の健康管理の一環として捉えることが非常に重要です。
初心者でも安心!愛犬が歯磨きを好きになるための5ステップ

「歯磨きが大切なのは分かったけど、うちの子は口を触られるのすら嫌がる…」そんな飼い主さんのために、無理なく歯磨きに慣れさせるための具体的な5つのステップをご紹介します。焦りは禁物です。愛犬のペースに合わせて、遊びやコミュニケーションの一環として、楽しみながら進めていくのが成功への近道です。
ステップ①:口周りを触られることに慣れさせる
最初の目標は、歯を磨くことではなく、「口周りを触られることは怖くない」と愛犬に教えてあげることです。
まずは、愛犬がリラックスしている時に、優しく声をかけながら顔や口の周りを撫でてあげましょう。この時、いきなり口をこじ開けようとしたり、無理に唇をめくったりしてはいけません。
最初はほんの数秒触るだけでOKです。上手にできたら、たくさん褒めてご褒美のおやつをあげましょう。「口を触られる=良いことがある」と愛犬が学習することが重要です。このステップを数日間繰り返し、愛犬が抵抗なく口周りを触らせてくれるようになったら、次のステップに進みます。
ステップ②:歯磨きジェルやペーストの味に慣れさせる
次に、歯磨きに使う歯磨き粉(ジェルやペースト)の味に慣れてもらい、歯磨きへの抵抗感を減らします。
犬用の歯磨き粉には、チキン風味やミルク風味など、犬が好む味がたくさんあります。まずは指先に少量取り、匂いを嗅がせたり、舐めさせてあげたりしましょう。美味しい味だと分かれば、歯磨きに対する警戒心が薄れていきます。
このステップのポイントは、歯磨き粉を「特別なご褒美」のように演出することです。飼い主さんが美味しそうに舐めさせてあげることで、愛犬も安心して受け入れやすくなります。この美味しい味に慣れてくれたら、次のステップはもう目前です。
ステップ③:指サックや歯磨きシートで歯に触れてみる
歯ブラシの前に、まずは飼い主さんの指で歯に触れる感覚に慣れさせます。
ステップ②で使った美味しい歯磨きジェルを指につけ、まずは唇を優しくめくって歯や歯茎にそっと触れてみましょう。最初は前歯から始め、嫌がらないようであれば、徐々に奥歯の方にも触れていきます。
指の感触に慣れてきたら、指サック型の歯ブラシや、指に巻き付けて使う歯磨きシートを試してみるのも良い方法です。飼い主さんの指の感覚で力加減を調整しやすいため、愛犬に不快感を与えにくいというメリットがあります。この段階でも、上手にできたら褒めることを忘れないようにしましょう。
ステップ④:歯ブラシを口に入れる練習をする
いよいよ歯ブラシの登場ですが、ここでも焦らず、歯ブラシ自体に慣れてもらうことから始めます。
まずは、歯ブラシに美味しい歯磨きジェルをつけ、おもちゃのように匂いを嗅がせたり、舐めさせてあげたりしましょう。歯ブラシは「敵」ではなく、「美味しいものが付いている良いもの」だと認識させることが目的です。
愛犬が歯ブラシに警戒しなくなったら、優しく口の中に入れてみます。この時、ゴシゴシ磨く必要はありません。歯に数秒間そっと当てるだけで十分です。これを繰り返し、歯ブラシが口の中に入ることに抵抗がなくなったら、最終ステップに進みましょう。
ステップ⑤:前歯から少しずつ歯ブラシで磨いてみる
全ての準備が整ったら、いよいよ歯ブラシで磨くことに挑戦します。
まずは、比較的嫌がりにくい前歯の外側から、1〜2本だけ優しく磨いてみましょう。この時も、短時間で終わらせることが大切です。上手にできたら、すぐに褒めて歯磨きを終了します。
これを毎日繰り返し、少しずつ磨く歯の本数を増やしていきます。「全部の歯を完璧に磨かなければ」と気負う必要はありません。最初のうちは、歯磨きを「楽しい時間」として習慣づけることが最も重要です。このステップを根気強く続けることで、愛犬は歯磨きを受け入れてくれるようになるでしょう。
獣医師推奨!犬の正しい歯磨きのやり方とコツ

歯磨きに慣れてきたら、次はその「質」を高めていきましょう。自己流でゴシゴシ磨いてしまうと、歯茎を傷つけたり、犬に痛みを与えてしまったりして、かえって歯磨き嫌いの原因になることも。ここでは、獣医師が推奨する正しい歯磨きの方法と、効果を最大限に引き出すためのコツを、まるで動画を見るように分かりやすく解説します。
準備するもの:犬用歯ブラシと歯磨き粉の選び方
効果的で安全な歯磨きのためには、愛犬に合った歯ブラシと歯磨き粉を選ぶことが最初のステップです。
歯ブラシは、犬の口の大きさに合ったヘッドのものを選びましょう。小型犬にはヘッドが小さいもの、大型犬には大きいものと、サイズを合わせることが重要です。毛の硬さは、歯茎を傷つけないように「やわらかめ」が基本です。360度毛がついているタイプは、角度を気にせず磨けるので初心者の方におすすめです。
歯磨き粉は、犬が好む味のものを選ぶのが一番ですが、すすぎが不要なものを選んでください。人間用の歯磨き粉は、犬が中毒を起こす可能性のあるキシリトールが含まれていることがあるため、絶対に使用してはいけません。
磨き方の基本:歯と歯茎の境目を45度の角度で優しく
歯磨きで最も重要なポイントは、歯と歯茎の境目にある「歯周ポケット」の汚れを掻き出すことです。
歯周病菌はこの歯周ポケットに潜んでいます。歯ブラシを歯の表面に対して45度の角度で当て、歯周ポケットに毛先が入るように意識してください。そして、力を入れずに、小刻みに優しくブラシを動かします。
力任せにゴシゴシ磨くのは絶対にやめましょう。歯の表面のエナメル質や歯茎を傷つける原因になります。鉛筆を持つような軽い力で、あくまでソフトに磨くことが基本です。全ての歯を磨くのに、1〜2分もかければ十分です。短時間で集中して行いましょう。
特にココを磨く!歯石が付きやすい犬歯と奥歯の磨き方
全ての歯を均等に磨くのが理想ですが、特に汚れが溜まりやすい「重点ポイント」を知っておくと効率的です。
犬の歯で特に歯石が付きやすいのは、唾液腺の開口部が近い「上の奥歯(臼歯)」と、構造的に汚れが溜まりやすい「上の犬歯」です。歯磨きに慣れていないうちは、まずこの重点ポイントだけでも磨くことを目標にしましょう。
奥歯を磨く際は、片方の手で優しく頬(マズル)を持ち上げると、唇がめくれて磨きやすくなります。犬歯は長くて目立つ歯なので、比較的磨きやすいはずです。まずは外側から始め、慣れてきたら歯の裏側も磨けるようにチャレンジしてみてください。
褒めるのが最重要!歯磨きを楽しい時間にするコツ
どんなに正しい方法で磨いても、愛犬が嫌がっていては長続きしません。歯磨きを「楽しいしつけの時間」に変えることが成功の鍵です。
歯磨きの前後には、必ず「えらいね!」「上手だね!」とたくさん褒めてあげましょう。そして、終わった後には大好きなおやつをあげたり、おもちゃで遊んであげたりする「特別なご褒美」を用意します。
こうすることで、犬は「歯磨きを我慢すれば、その後に良いことがある」と学習し、歯磨きに対してポジティブなイメージを持つようになります。叱ったり、無理やり押さえつけたりするのは逆効果です。飼い主さんがリラックスして、楽しい雰囲気を作ってあげることを常に心がけてください。
どうしても嫌がる・暴れる!レベル別の原因と対処法

正しいステップを踏んでも、どうしても歯磨きを嫌がって暴れてしまう子もいます。その行動の裏には、必ず何かしらの原因が隠されています。ここでは、愛犬の「嫌がりレベル」に合わせて、考えられる原因と具体的な対処法を解説します。愛犬の気持ちに寄り添い、適切なアプローチを見つけていきましょう。
レベル1:口を触られるのを嫌がる子の慣れさせ方
口を触られること自体に慣れていない、または過去に嫌な経験がある子がこのレベルに当てはまります。
この場合、原因は「未知への恐怖」や「トラウマ」です。まずは歯磨きのステップ①「口周りを触られることに慣れさせる」にじっくりと時間をかけて取り組みましょう。焦りは禁物です。
対処法としては、食事の時間を利用するのが効果的です。フードをあげる前に、一瞬だけ口元に触れてから「よし」と合図して食べさせる、という練習を繰り返します。こうすることで、「口を触られる=ご飯がもらえる」という嬉しい結びつきが生まれます。歯磨きとは切り離し、まずは口周りのスキンシップから信頼関係を再構築しましょう。
レベル2:歯ブラシを見ると逃げてしまう子への対処法
口は触らせてくれるけれど、歯ブラシを見ただけで逃げたり隠れたりしてしまうケースです。
原因は、歯ブラシという「物」に対する警戒心や恐怖心です。硬いブラシが口に入る感覚や、過去に強く磨かれて痛かった経験がトラウマになっている可能性があります。
この場合の対処法は、歯ブラシのイメージをポジティブなものに変えることです。歯ブラシを犬の目に付く場所に普段から置いておき、見慣れさせましょう。さらに、歯ブラシの先に美味しいペーストを付けて、舐めさせる練習(歯磨きステップ②、④)を重点的に行います。「歯ブラシ=美味しいおやつが出てくる魔法の棒」だと認識を変えてあげることが目標です。
レベル3:噛み付いて抵抗する子の最終手段
歯磨きをしようとすると、本気で唸ったり、噛み付いてきたりする最も深刻なレベルです。
原因は、強い恐怖心や、口の中に痛みがある可能性が考えられます。無理やり押さえつけて歯磨きをしようとすると、飼い主さんとの信頼関係が崩壊し、状況はさらに悪化します。このレベルの場合、自己流で解決しようとするのは非常に危険です。
まずは、動物病院やドッグトレーナーといった専門家に相談することを強く推奨します。口の中に痛みの原因となる歯周病などが隠れていないか、獣医師に診てもらうことが最優先です。その上で、専門家の指導のもと、正しいトレーニング方法で少しずつ慣らしていく必要があります。決して飼い主さん一人で抱え込まないでください。
注意:痛みが原因かも?動物病院に相談するケース
これまで平気だったのに、急に歯磨きを嫌がるようになった場合は、口の中に痛みを抱えているサインかもしれません。
犬は痛みを我慢してしまう生き物です。しかし、歯周病が進行して歯茎が腫れていたり、歯がグラグラしていたり、あるいは口内炎ができていたりすると、歯ブラシが当たることで激しい痛みを感じます。
「急に嫌がるようになった」「特定の場所だけ触らせない」「よだれが増えた」「血が混じる」などの変化が見られたら、すぐに動物病院を受診してください。痛みの原因を取り除かない限り、歯磨きを受け入れてくれることはありません。まずは愛犬を苦痛から解放してあげることが、飼い主さんの務めです。
歯磨きが苦手な子でもできる!補助的なデンタルケアグッズ4選

毎日の歯磨きが理想と分かっていても、どうしても愛犬が受け入れてくれない、あるいは時間がなくて完璧にできない日もあります。そんな時に役立つのが、歯磨きの補助的な役割を果たすデンタルケアグッズです。ただし、これらはあくまで「補助」であり、歯ブラシの代わりにはならないことを理解しておきましょう。ここでは代表的な4つのグッズと、その賢い使い方をご紹介します。
①噛むだけで歯垢除去!歯磨きガムの選び方と注意点
歯磨きガムは、犬が噛むことで歯の表面の歯垢を物理的にこすり落とす効果が期待できる、手軽なケアグッズです。
メリットは、おやつ感覚で与えられるため、犬が喜んでケアに応じてくれる点です。選ぶ際は、愛犬の体の大きさに合ったサイズで、ある程度の硬さと弾力があるものを選びましょう。また、歯垢除去効果が科学的に証明されている製品には「VOHC(米国獣医口腔衛生協議会)」の認定マークが付いているので、一つの目安になります。
デメリットとしては、噛む回数が少ないと効果が薄いことや、カロリーオーバーになりやすい点が挙げられます。丸呑みして喉に詰まらせる危険もあるため、必ず飼い主さんが見ている前で与えるようにしてください。
②遊びながらケア!デンタルおもちゃの活用法
デンタルおもちゃは、表面に凹凸や溝がある特殊な形状をしており、犬が噛んで遊ぶことで歯垢を絡め取る仕組みです。
最大のメリットは、犬が遊びに夢中になっている間に、自然とデンタルケアができてしまう手軽さにあります。犬が飽きないように、様々な形状や硬さのものを試してみると良いでしょう。おもちゃの溝に歯磨きペーストを塗り込んであげると、より効果が高まります。
ただし、これも歯磨きガムと同様、噛む場所や時間によっては十分に効果が得られない可能性があります。また、おもちゃが破損して破片を飲み込んでしまう危険性もゼロではありません。定期的に製品の傷み具合をチェックし、古くなったら新しいものに交換することが大切です。
③シートで拭くだけ!歯磨きシートの使い方
歯磨きシートは、指に巻き付けて歯の表面を拭うことで、付着した歯垢や食べかすを取り除くグッズです。
歯ブラシを嫌がる子でも、飼い主さんの指の感触なら受け入れてくれやすいというメリットがあります。歯磨きに慣れさせるための初期ステップとしても非常に有効です。歯ブラシのように細かい部分を磨くのは難しいですが、歯の表面全体のケアを手軽に行えます。
デメリットは、歯と歯茎の境目にある歯周ポケットの汚れまでは掻き出せない点です。あくまで歯の表面をきれいにするものだと考えましょう。歯ブラシでのケアを最終目標としつつ、どうしてもできない日の代替ケアとして活用するのがおすすめです。
④舐めるだけでもOK!歯磨きジェルの効果
歯磨きジェルの中には、口内の細菌の増殖を抑える成分が含まれており、舐めさせるだけでも口臭予防などの効果が期待できる製品があります。
歯ブラシや指を口に入れることすら嫌がる子にとって、最初のステップとして取り入れやすいのがこのタイプです。美味しい味がついているものが多く、ご褒美として与えることで、口内ケアへの抵抗感を和らげる助けになります。
もちろん、物理的に歯垢をこすり落とす効果はないため、これだけでデンタルケアが完結するわけではありません。しかし、何もしないよりは格段に良い選択です。このジェルで味に慣れてもらい、少しずつ指で塗る、シートで拭う、といった次のステップへつなげていくための「架け橋」として活用しましょう。
犬の歯磨きに関するよくある質問
ここでは、犬の歯磨きに関して飼い主さんから特によく寄せられる質問にお答えします。日々のケアで生まれる小さな疑問を解消して、もっと自信を持って愛犬のデンタルケアに取り組んでいきましょう。
Q1. 犬の歯磨きはいつから始めるべきですか?
結論として、歯磨きは乳歯が生え揃う生後3〜4ヶ月頃から始めるのが理想的です。
子犬の頃は好奇心旺盛で、新しいことを受け入れやすいため、歯磨きを楽しい習慣として身につけさせる絶好の機会です。永久歯に生え変わる生後6〜7ヶ月頃までには、口や歯に触られることに慣れさせておきましょう。成犬になってから始めるよりも、スムーズに歯磨きを受け入れてくれる可能性が格段に高まります。もちろん、成犬やシニア犬からでも遅すぎることはありません。根気強く続ければ、何歳からでも習慣にすることは可能です。
Q2. 人間用の歯磨き粉を使っても大丈夫ですか?
絶対にダメです。人間用の歯磨き粉の使用は、愛犬の健康を害する危険があるため、絶対に使用しないでください。
人間用の歯磨き粉には、犬が飲み込むと中毒症状を起こす可能性がある「キシリトール」や、泡立ち成分の「発泡剤」が含まれています。犬は口をゆすぐことができないため、これらの成分を全て飲み込んでしまいます。必ず、犬専用に開発された、飲み込んでも安全な成分で作られた歯磨き粉(ジェルやペースト)を使用するようにしてください。
Q3. すでに歯石がついてしまった場合はどうすればいいですか?
一度硬く付着してしまった歯石は、家庭での歯磨きで取り除くことはできません。無理に取ろうとすると歯や歯茎を傷つけるため、必ず動物病院に相談してください。
動物病院では、全身麻酔をかけた上で、「スケーラー」という専門の器具を使って安全かつ綺麗に歯石を除去(スケーリング)してくれます。無麻酔での歯石除去を謳うサービスもありますが、歯の裏側や歯周ポケット内の歯石は取れず、犬に恐怖心を与えるリスクがあるため、獣医師は推奨していません。まずはかかりつけの獣医師に相談し、適切な処置を受けることが重要です。
Q4. 歯磨きのご褒美には何がいいですか?
歯磨きのご褒美は、愛犬が「特別に嬉しい」と感じるものであれば何でも構いませんが、低カロリーで小さいものがおすすめです。
毎日のことなので、カロリーの高いおやつを与えすぎると肥満の原因になります。普段のフードを数粒だけ特別な手つきであげる、小さくちぎったささみジャーキー、あるいはデンタルガムをご褒美にするのも良いでしょう。また、おやつだけでなく、「よくできたね!」という飼い主さんの明るい声や、思いっきり撫でてあげること、ボール遊びなども立派なご褒美になります。愛犬が最も喜ぶことを見つけてあげましょう。
まとめ:愛犬の健康長寿のために、今日から正しい歯磨きを習慣にしよう

この記事では、犬の歯磨きの理想的な頻度が「毎日」、最低でも「3日に1回」である理由から、正しい磨き方、嫌がる子への対処法までを詳しく解説しました。
歯磨きを怠ることは、単なる口臭だけでなく、愛犬を苦しめる歯周病や、命に関わる全身の病気につながるリスクを高めてしまいます。最初は少し大変に感じるかもしれませんが、ご紹介した5つのステップで少しずつ慣らしていけば、歯磨きは愛犬との大切なコミュニケーションの時間に変わるはずです。
完璧を目指す必要はありません。まずは口元を触って褒めてあげることから始めてみましょう。その小さな一歩が、愛犬の痛みのない快適な生活と、健康で幸せな未来を守ることに繋がります。今日からあなたと愛犬に合ったペースで、デンタルケアを始めてみませんか。
大切なペットの移動にはペットタクシー「かるたく」がおすすめ

ペットタクシー「かるたく」は、愛玩動物飼養管理士の資格を持つドライバーが、大切なペットを安心・安全に送迎するサービスです。
動物病院への送迎が全体の55.9%を占め、ペットの体調に配慮した運転を心掛けています。料金は事前にシミュレーションでき、明瞭な価格設定が魅力です。車内は広々としており、多頭飼いの方も安心。
ペット用ラグジュアリークッションやスロープを完備し、快適な移動をサポートします。さらに、乗車毎の除菌・清掃・消臭を徹底し、清潔な環境を提供。
ペットホテル、引っ越し、トリミング、旅行など、さまざまなシーンでご利用いただけます。今なら最大50%オフのキャンペーン実施中。大切なペットとの移動に、ぜひ「かるたく」をご利用ください。