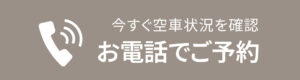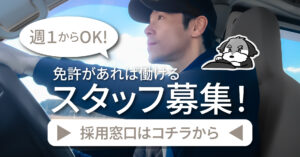愛犬が他の犬に会うたびに吠えたり、隠れたりする「犬見知り」な姿に、心を痛めていませんか。散歩が憂鬱になったり、ドッグランに連れて行ってあげられないことにもどかしさを感じたりするのは、あなただけではありません。
この記事では、犬見知りの根本的な原因から、成犬からでも実践できる具体的な直し方、そして絶対にやってはいけないNG対応まで、専門家の知見を基に徹底解説します。
この記事を読めば、愛犬の気持ちを理解し、正しいステップで犬見知りを克服する方法が分かります。愛犬との毎日をもっと楽しく、豊かなものにするための一歩を、ここから踏み出しましょう。
まずは結論!あなたの愛犬の犬見知りは改善できます

愛犬の犬見知りに悩む飼い主さんは少なくありません。しかし、正しい知識と適切なトレーニングを行えば、その行動は改善できます。大切なのは、犬の気持ちを理解し、焦らずその子のペースに合わせてあげることです。この記事では、犬見知りのサインから原因、そして具体的な克服法までを分かりやすく解説していきます。
犬見知りとは?よく見られる4つの行動サイン
犬見知りとは、犬が他の犬や、時には人間に対して、恐怖や不安、警戒心を抱くことで見せる一連の行動を指します。犬からの「ちょっと怖いよ」「今は近づかないで」というサインであり、決して性格が悪いわけではありません。このサインを正しく理解することが、問題解決の第一歩となります。行動の背景には、社会化期の経験不足や過去のトラウマなど、様々な要因が隠されています。まずは、愛犬が発するサインに気づいてあげましょう。
①他の犬から隠れる・逃げる
他の犬の姿が見えた途端、飼い主の後ろに隠れたり、その場から逃げ出そうとしたりするのは、犬見知りの典型的なサインです。
これは、対象から物理的に距離をとることで、自分自身の安全を確保しようとする、非常に分かりやすい回避行動と言えます。犬は「これ以上近づくと危険かもしれない」という強い不安を感じています。無理に引き戻そうとせず、まずは愛犬が安心できる距離まで離れてあげることが重要です。
②吠える・唸る
「唸る」「吠える」という行動は、一見すると攻撃的に見えるかもしれません。しかし、その多くは「怖いからあっちへ行って!」という恐怖心から来ています。
相手を威嚇することで、それ以上近づかせないようにしているのです。これは、犬が自分の身を守るための最後の手段の一つです。このサインを無視して無理に近づけると、恐怖からパニックになり、相手の犬に噛みついてしまうといった、より深刻な事態に発展する可能性もあるため注意が必要です。
③体を固まらせる・震える
他の犬と遭遇した際に、ピタッと動きを止めて体を固まらせたり、小刻みに震えたりするのも、強いストレスや恐怖を感じているサインです。
これは、犬が「フリーズ(凍りつき)」と呼ばれる状態に陥っていることを示します。どうしていいか分からず、思考が停止してしまっているのです。この状態で無理に動かそうとすると、犬の混乱を助長させてしまいます。まずはその場を静かに離れ、愛犬を落ち着かせてあげることが最優先です。
④目をそらす・あくびを繰り返す
犬の世界では、相手の目を見つめ続けることは敵意のサインと見なされることがあります。そのため、犬見知りの犬は、他の犬と出会うと意図的に目をそらし、敵意がないことを示そうとします。
また、ストレスを感じた時に自分を落ち着かせるための行動として、頻繁にあくびをしたり、鼻をペロペロ舐めたりすることもあります。これらは「カーミングシグナル」と呼ばれ、犬が「穏便に済ませたい」と思っている証拠です。
無理に治す必要はない?犬見知りを克服するメリット
愛犬が他の犬を苦手なら、無理に交流させる必要はない、と考える方もいるかもしれません。しかし、犬見知りを克服することには、犬と飼い主の双方にとって大きなメリットがあります。
犬見知りの克服は、単に他の犬と仲良くさせることだけが目的ではなく、愛犬と飼い主の生活の質(QOL)を向上させることが本質です。ストレス要因が減ることで、日々の生活がより豊かで安心できるものに変わっていくでしょう。
①愛犬のストレスが減り、散歩がもっと楽しくなる
犬見知りを克服する最大のメリットは、愛犬自身のストレスが大幅に軽減されることです。散歩中に他の犬とすれ違うたびに恐怖を感じるのは、犬にとって大きな苦痛です。
このストレスから解放されれば、散歩はもっとリラックスできる楽しい時間になります。飼い主さんも「いつ他の犬に会うか」とビクビクすることなく、純粋に愛犬との散歩を楽しめるようになるでしょう。穏やかな気持ちで歩く飼い主さんの姿は、犬にも安心感を与えます。
②ドッグランなど、お出かけ先の選択肢が広がる
犬見知りが改善されれば、これまで諦めていた場所にも行けるようになります。
例えば、広々としたドッグランで思いっきり走り回らせてあげたり、ドッグカフェで一緒にくつろいだり、犬同伴OKの旅行先に出かけたりと、愛犬との楽しみ方が格段に広がります。様々な場所に一緒に行けるようになることは、愛犬との絆をさらに深め、かけがえのない思い出をたくさん作ることにも繋がるでしょう。
③災害時や預ける時など、いざという時に安心
犬見知りは、普段の生活だけでなく、万が一の時にも大きな問題となる可能性があります。
例えば、災害時の避難所では、多くの人や他の動物と一緒に過ごさなければなりません。また、ペットホテルや動物病院に預ける際にも、他の犬の存在は避けられません。犬見知りを克服しておくことは、このような非日常的な状況下で愛犬が感じるストレスを最小限に抑え、心身の健康を守るための重要な備えとなるのです。
なぜ?犬が犬見知りになる4つの主な原因

愛犬の犬見知りを改善するためには、まずその行動の裏にある原因を理解することが不可欠です。原因は一つだけでなく、複数の要因が複雑に絡み合っていることも少なくありません。ここでは、犬が犬見知りになる代表的な4つの原因を解説します。原因を知ることで、愛犬に合った適切なアプローチ方法が見えてくるはずです。
①社会化期の経験不足
犬見知りになる最も一般的な原因は、「社会化期」の経験不足です。社会化期とは、一般的に子犬が生後3週齢から12〜16週齢頃までの、好奇心が恐怖心を上回る特別な時期のことです。
この時期に、他の犬や人間、様々な物や音に触れて良い経験を積むことで、順応性のある社会性を身につけます。この大切な時期に他の犬との接触が少なかったり、室内だけで過ごしたりすると、未知の対象に対して過剰な恐怖や警戒心を抱きやすくなり、犬見知りの原因となってしまうのです。
②過去の嫌な経験やトラウマ
過去に他の犬からしつこく追いかけられた、攻撃されたといったネガティブな経験は、犬の心に深い傷を残し、トラウマとなることがあります。
一度「犬は怖いものだ」と学習してしまうと、その記憶がよみがえり、他のすべての犬に対しても恐怖を感じるようになってしまいます。飼い主が気づかないような些細な出来事が、犬にとっては大きなトラウマになっているケースも少なくありません。特に臆病な性格の犬ほど、一度の嫌な経験が犬見知りに直結しやすい傾向があります。
③飼い主の過剰な反応や不安
愛犬を思うあまりの飼い主の行動が、意図せず犬見知りを助長していることがあります。例えば、散歩中に他の犬が見えた途端、飼い主さんが「どうしよう、吠えちゃうかも」と緊張してリードを強く握りしめたり、慌てて抱き上げたりすると、その不安が犬に伝わってしまいます。
犬は「飼い主が緊張している。やっぱりあの犬は危険なんだ」と学習し、ますます警戒心を強めてしまうのです。犬は飼い主の感情を敏感に察知するため、まずは飼い主自身が落ち着いて堂々とした態度でいることが非常に重要です。
④犬自身の性格や持って生まれた気質
人間と同じように、犬にも一頭一頭、持って生まれた性格や気質があります。
遺伝的に警戒心が強く、慎重で臆病な性格の犬は、もともと犬見知りになりやすい傾向があると言えます。このような犬は、新しい環境や刺激に慣れるまでに時間がかかることが多いです。しかし、持って生まれた気質だからと諦める必要はありません。その子の個性を尊重し、時間をかけて丁寧に社会性を育んでいくことで、過度な恐怖心を和らげ、穏やかに過ごせるように導いてあげることは十分に可能です。
【5ステップで実践】犬見知りの正しい治し方・克服トレーニング

ここからは、実際に犬見知りを克服するための具体的なトレーニング方法を5つのステップでご紹介します。大切なのは、結果を急がず、愛犬のペースに合わせてスモールステップで進めることです。一つクリアできたらたくさん褒めて、成功体験を積ませてあげましょう。飼い主さんの根気と愛情が、愛犬を変える一番の力になります。
ステップ1:基本の信頼関係を築き直す
トレーニングを始める前に、何よりもまず飼い主と愛犬との間の信頼関係をしっかりと築くことが不可欠です。犬は、信頼する飼い主がそばにいれば「この人がいれば大丈夫」と安心感を得ることができます。
この安心感が、未知の対象に立ち向かう勇気の土台となります。日頃から「おすわり」や「まて」などの基本的なコマンドトレーニングを行ったり、一緒に遊んだりする時間を大切にしましょう。飼い主が頼れるリーダーであることを示すことで、犬は自信を持って行動できるようになります。
ステップ2:他の犬がいる環境に「見るだけ」で慣らす
まずは、他の犬がいても愛犬が恐怖を感じない、遠い距離からスタートします。公園のベンチなどから、遠くで散歩している犬を「見るだけ」の練習です。
この時、愛犬が落ち着いていられたら、すかさず褒めて特別なおやつをあげましょう。もし吠えたり興奮したりするようなら、それは距離が近すぎるサインです。もっと遠くまで離れて、愛犬がリラックスできる距離を見つけてください。「他の犬が見える=良いことがある」というポジティブな関連付けを根気強く行っていくことが、このステップの目的です。
ステップ3:おやつを使い「犬=嬉しい」のイメージをつける
ステップ2に慣れてきたら、他の犬が視界に入った瞬間に、大好きなおやつを与える練習をします。犬が他の犬に気づく→飼い主を見る→おやつをもらう、という流れを何度も繰り返します。
これを続けることで、犬の頭の中では「他の犬が現れると、飼い主さんから最高のご褒美がもらえる!」という嬉しい予測が生まれます。恐怖や警戒の対象であった他の犬の存在が、徐々に「良いことの合図」へと変わっていくのです。この条件付けが、犬の感情を根本から変える鍵となります。
ステップ4:すれ違う練習(ディスタンス・トレーニング)
次に、他の犬と距離を保ったまま歩いてすれ違う練習に移ります。「ディスタンス・トレーニング」と呼ばれるこの手法は、相手に近づきすぎず、安全な距離を保つことがポイントです。
散歩コースの広い道などを選び、向こうから犬が来たら、道の端に寄って愛犬を自分の隣に座らせます。そして、犬が通り過ぎるまでおやつを与え続け、落ち着いていられたらたくさん褒めてあげましょう。決して無理に挨拶させようとせず、穏やかにすれ違う経験を何度も積ませることが大切です。
ステップ5:相性の良い穏やかな犬と挨拶させてみる
すべてのステップが順調に進み、愛犬が他の犬に対して落ち着いていられるようになったら、最終段階として挨拶の練習を考えます。ただし、相手選びは非常に重要です。
必ず、穏やかで社交的な、犬慣れしている犬を相手に選んでください。友人や知人の犬に協力してもらうのが理想的です。最初はリードをつけたまま、お互いのお尻の匂いを嗅がせるところから始めます。数秒間の短い挨拶で終え、うまくいったらすぐにその場を離れてたくさん褒めてあげましょう。ポジティブな経験で締めくくることが成功の秘訣です。
逆効果!犬見知りを悪化させるNGな対応

愛犬の犬見知りを治したい一心で取る行動が、実は逆効果となり、問題をさらに悪化させてしまうことがあります。犬の気持ちを無視したアプローチは、恐怖心を増幅させ、飼い主への不信感にも繋がりかねません。ここでは、飼い主がやりがちなNG対応を3つご紹介します。良かれと思ってやっていないか、ご自身の行動を振り返ってみましょう。
無理やり他の犬がいる場所に連れて行く・挨拶させる
犬見知りを克服させたいからといって、いきなりドッグランに連れて行ったり、散歩中に無理やり他の犬に近づけて挨拶させたりするのは絶対にやめましょう。犬にとっては、最も怖いと感じる対象に無理やり向き合わされることになり、パニックやトラウマを悪化させるだけです。
これは、高所恐怖症の人をいきなり高層ビルの屋上に連れて行くようなものです。犬は飼い主を「自分を守ってくれない存在」と認識し、信頼関係まで損なわれかねません。
吠えたり逃げたりした時に叱る
他の犬に対して吠えたり、逃げようとしたりした時に、「ダメでしょ!」と大きな声で叱っていませんか。犬がこれらの行動をとるのは、恐怖や不安を感じているからです。
その気持ちを理解せずに叱りつけると、犬は「怖いと感じているのに、さらに飼い主にまで怒られた」と混乱してしまいます。叱られることで恐怖心が消えることはなく、むしろ「他の犬に会うと、嫌なこと(叱られること)が起きる」と学習し、犬見知りがさらに強化されてしまう悪循環に陥ります。
飼い主が緊張してリードを強く引っ張る
散歩中に他の犬を見つけた飼い主が、緊張のあまりリードをグッと強く短く持つことがあります。この力強い張りは、犬に即座に伝わります。
犬は「リードが張っている。何か危険が迫っているんだ!」と察知し、飼い主の緊張を自分のものとして感じ取ってしまいます。飼い主の不安が犬の不安を煽り、警戒心を最大限に高めてしまうのです。犬を落ち着かせたいなら、まずは飼い主自身が深呼吸をし、リラックスしてリードを緩やかに保つことを意識してください。
成犬や保護犬の犬見知りも治せる?

「うちの子はもう成犬だから」「保護犬で過去が分からないから」と、犬見知りの改善を諦めていませんか。確かに子犬期に比べて時間や根気は必要かもしれませんが、決して不可能ではありません。成犬や保護犬だからこそ、より丁寧なアプローチと深い愛情が求められます。彼らのペースを尊重し、心を開いてくれるのをじっくりと待ちましょう。
成犬からでも改善は可能!ただし焦りは禁物
成犬の犬見知りを改善することは十分に可能です。しかし、子犬の社会化期のように物事を柔軟に吸収できる時期は過ぎているため、新しい学習には時間がかかることを理解しておく必要があります。
成犬のトレーニングで最も重要なのは「焦らないこと」です。長年かけて形成された恐怖心や警戒心を解きほぐすには、何か月、あるいは年単位の時間がかかることもあります。小さな進歩を見つけては褒めることを繰り返し、気長に取り組む姿勢が成功への鍵となります。
保護犬の場合は、まず安心できる環境作りを最優先に
保護犬の場合、過去にどのような経験をしてきたか分からないケースがほとんどです。虐待や育児放棄など、人や他の犬に対して強い不信感を抱く原因となるトラウマを抱えている可能性も考慮しなければなりません。
トレーニングを始める前に、まずは新しい家族と家が「絶対に安全な場所」であることを時間をかけて教えてあげる必要があります。無理に何かをさせようとせず、犬が自ら心を開いてくれるまで、静かに見守り、安心できる環境を提供することを最優先にしてください。
時間をかけて少しずつの進歩を褒めてあげることが大切
成犬や保護犬のトレーニングでは、結果を急ぐあまり、飼い主が設定した高い目標を犬に押し付けてしまいがちです。しかし、大切なのは犬の目線に立つことです。
昨日まで10m先で固まっていたのが、今日は9mまで近づけた。それだけでも、犬にとっては大きな勇気を出した結果であり、素晴らしい進歩です。どんなに小さな変化でも見逃さず、大げさなくらいに褒めてあげましょう。その積み重ねが犬の自信となり、次の一歩を踏み出す力に繋がっていきます。
どうしても改善しない場合は専門家を頼ろう

セルフケアでトレーニングを続けても、なかなか犬見知りが改善しない、あるいは行動が悪化してしまう場合は、一人で抱え込まずに専門家の力を借りることを検討しましょう。犬の行動には、飼い主だけでは気づけない原因が隠れていることもあります。専門家は、客観的な視点から問題点を分析し、その子に合った最適な解決策を提案してくれます。
かかりつけの獣医師に相談する
まずは、日頃から愛犬の健康状態をよく知る、かかりつけの獣医師に相談してみましょう。犬見知りの行動の背景に、実は体のどこかの痛みや不調、あるいはホルモンバランスの乱れといった医学的な問題が隠れている可能性もゼロではありません。
特に、急に犬見知りがひどくなったような場合は、病気のサインである可能性も疑う必要があります。まずは身体的な問題がないかを確認してもらうことが、適切な対応への第一歩となります。
ドッグトレーナーのカウンセリングを受ける
ドッグトレーナーは、犬のしつけや行動トレーニングの専門家です。数多くの犬を見てきた経験から、愛犬の行動の理由を的確に分析し、具体的なトレーニングプランを立ててくれます。
特に、飼い主と犬との関係性や、日常的な接し方に問題が隠れている場合、プロの視点からのアドバイスは非常に有効です。出張トレーニングやしつけ教室など、様々な形態があるので、自分と愛犬に合ったトレーナーを探してみましょう。
犬の行動診療科を受診する
犬見知りの症状が極端に重い場合や、恐怖から攻撃行動にまで発展してしまっている場合は、「行動診療科」という専門の診療科を受診する選択肢もあります。
行動診療科の獣医師は、行動学と精神医学の両面からアプローチし、より専門的な診断と治療を行います。場合によっては、犬の不安を和らげるためのサプリメントや、精神安定薬などを使った薬物療法をトレーニングと並行して行うこともあります。これは、治療の最終手段の一つと捉えましょう。
犬見知りに関するよくある質問
ここでは、犬見知りの飼い主さんから特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。日々の生活の中で直面する具体的な悩みや疑問を解消し、より安心してトレーニングに取り組むための参考にしてください。正しい知識を持つことが、愛犬とのより良い関係に繋がります。
散歩中に他の犬と出会ってしまったら、どうすればいいですか?
まずは、飼い主が冷静でいることが最も重要です。慌ててリードを引いたり、大声を出したりすると、犬の不安を煽ってしまいます。
他の犬に気づいたら、すぐに進路を変えてその場を離れるか、道の端に寄って犬を自分の背後に座らせ、おやつなどで注意を自分に向けさせましょう。相手が通り過ぎるまで落ち着いて待つことができたら、たくさん褒めてあげてください。無理に挨拶させる必要は全くありません。
犬見知りなのにドッグランに連れて行っても大丈夫ですか?
犬見知りが改善されていない段階で、いきなりドッグランに連れて行くのは絶対に避けるべきです。
たくさんの犬が自由に走り回るドッグランは、犬見知りの犬にとっては非常に刺激が強く、極度の恐怖を感じる場所です。トラウマを悪化させるだけでなく、他の犬に怪我をさせてしまうリスクもあります。まずはこの記事で紹介したステップでトレーニングを積み、犬が他の犬の存在に慣れてから、空いている時間帯に短時間だけ試すなど、慎重に判断してください。
犬見知りを放置していると、どんな問題がありますか?
犬見知りを放置すると、犬自身が日常的に強いストレスを感じ続けることになります。
この慢性的なストレスは、免疫力の低下や問題行動の悪化など、心身の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。また、散歩や外出が困難になることで、犬と飼い主双方のQOL(生活の質)が低下してしまいます。さらに、トリミングサロンやペットホテル、動物病院などを利用する際に、犬にもスタッフにも大きな負担がかかることになります。
多頭飼いをすれば、犬見知りは自然に治りますか?
安易に「多頭飼いをすれば社会性が身について犬見知りが治るだろう」と考えるのは非常に危険です。
むしろ、犬見知りの先住犬にとって、新しくやってきた犬はテリトリーを脅かす大きなストレス源となり、関係が悪化するケースが少なくありません。多頭飼いを検討するのは、まず先住犬の犬見知りをある程度改善し、他の犬を受け入れる心の準備ができてからにしましょう。迎える際も、相性を慎重に見極め、段階的に慣らしていく必要があります。
まとめ:愛犬のペースを尊重し、楽しい散歩を目指そう

この記事では、犬見知りの原因から具体的な克服トレーニング、そして飼い主がやってはいけないNG対応までを詳しく解説しました。犬見知りは、けっして治らないものではありません。大切なのは、行動の裏にある愛犬の「怖い」「不安だ」という気持ちに寄り添い、その子のペースを何よりも尊重してあげることです。
他の犬と上手に遊べるようになることだけがゴールではありません。愛犬が、他の犬の存在を過度に恐れることなく、飼い主さんと一緒にリラックスして散歩を楽しめるようになること。それこそが、目指すべき最高の状態と言えるでしょう。
この記事で紹介した方法を参考に、ぜひ愛犬との信頼関係を深めながら、一歩ずつ前に進んでいきましょう。あなたの愛情と根気が、愛犬の未来を明るく照らすはずです。
大切なペットの移動にはペットタクシー「かるたく」がおすすめ

ペットタクシー「かるたく」は、愛玩動物飼養管理士の資格を持つドライバーが、大切なペットを安心・安全に送迎するサービスです。
動物病院への送迎が全体の55.9%を占め、ペットの体調に配慮した運転を心掛けています。料金は事前にシミュレーションでき、明瞭な価格設定が魅力です。車内は広々としており、多頭飼いの方も安心。
ペット用ラグジュアリークッションやスロープを完備し、快適な移動をサポートします。さらに、乗車毎の除菌・清掃・消臭を徹底し、清潔な環境を提供。
ペットホテル、引っ越し、トリミング、旅行など、さまざまなシーンでご利用いただけます。今なら最大50%オフのキャンペーン実施中。大切なペットとの移動に、ぜひ「かるたく」をご利用ください。