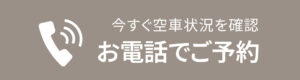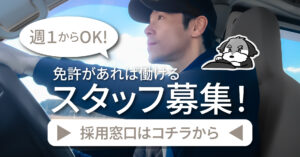愛犬の夜泣きが続き、「どうして鳴くの?」「ご近所迷惑になっていないか…」と眠れない夜を過ごしていませんか。その老犬の夜泣きは、単なるわがままではなく、体や心のつらいサインかもしれません。
この記事では、夜泣きの5つの主な原因を突き止め、具体的な対処法を分かりやすく解説します。
さらに、動物病院へ行くべきサインや、追いつめられがちな飼い主様の心のケアについても触れていきます。原因に合った正しいケアを実践し、愛犬とあなたの穏やかな夜を取り戻しましょう。
老犬の夜泣き、もう悩まない!原因と対策がわかる早見チェックリスト

まずは「うちの子の夜泣きの原因はどれだろう?」と、あたりをつけたい飼い主様のために、原因と対策が一目でわかるチェックリストを用意しました。
忙しい方や、すぐに結論を知りたい方は、この章で愛犬の状態を確認し、対応する対策を試してみてください。
あなたの愛犬はどのタイプ?夜泣きの原因をチェック
まずは、愛犬の夜泣きや日中の様子に当てはまるものがないか、チェックしてみましょう。
最も多く当てはまったものが、夜泣きの主な原因である可能性が高いです。複数の原因が絡み合っている場合もあるため、あくまで原因を探るヒントとしてご活用ください。
【認知機能の低下】
□ 昼間に寝ている時間が増え、夜に起きている
□ 部屋の隅や狭い場所で動けなくなる
□ 理由もなくウロウロと歩き回る(徘徊)
□ 飼い主を認識できないような素振りを見せる
【身体的な痛み】
□ 特定の場所を触られるのを嫌がる
□ 立ち上がったり、歩いたりするのをためらう
□ 寝ている時に「キャン」と鳴くことがある
□ 体を震わせていることがある
【生理的な要求】
□ 食事の間隔が長く、夜中にお腹が空いていそう
□ 寝る前に水をあまり飲んでいない
□ トイレの失敗が増えた
【不安やストレス】
□ 最近、引っ越しや家族構成の変化があった
□ 飼い主の姿が見えないと鳴き始める
□ 雷や花火など、大きな音を怖がるようになった
【原因別】今夜からできる対策クイックガイド
原因のあたりがついたら、次に対応する対策を試してみましょう。
ここでは、原因別に「今夜からできること」をまとめました。すぐに実行できることばかりなので、ぜひ試してみてください。詳しい方法は、後の章で一つひとつ丁寧に解説していきます。
| 原因の可能性 | 今夜からできる対策 |
|---|---|
| 認知機能の低下 | 昼間に少しでも多く日光浴をさせ、軽く遊んであげる |
| 身体的な痛み | クッション性の高いマットを敷き、寝床を快適にする |
| 生理的な要求 | 寝る少し前に、消化の良い軽食や少量の水を与える |
| 不安やストレス | 飼い主さんの匂いがついたタオルや服を寝床に置く |
| 生活リズムの乱れ | 日中の活動時間を少し増やし、寝る時間を一緒に過ごす |
老犬が夜泣きをする5つの主な原因
![]()
ここからは、夜泣きを引き起こす5つの主な原因について、より詳しく掘り下げていきます。
愛犬の行動と照らし合わせながら、なぜ夜泣きが起こるのか、その背景を深く理解していきましょう。原因を正しく知ることが、解決への第一歩となります。
①認知機能の低下(認知症):昼夜逆転や不安が原因に
老犬の夜泣きで最も多い原因の一つが、認知機能の低下です。
認知機能の低下とは、脳の老化によって、人間と同じように時間や場所の感覚が鈍くなったり、これまで出来ていたことが出来なくなったりする状態を指します。いわゆる「犬の認知症」と呼ばれるものです。
この状態になると、体内時計が乱れて昼夜が逆転し、夜間に起きて活動的になってしまいます。また、自分がどこにいるのか分からなくなったり、飼い主を認識できなくなったりする不安から、鳴き続けてしまうのです。徘徊や旋回行動(同じ場所をぐるぐる回る)といった行動が見られる場合は、認知機能の低下が強く疑われます。
②身体的な痛みや不快感:関節炎や床ずれ、病気のサインかも
言葉で痛みを伝えられない愛犬が、夜泣きで不調を訴えている可能性があります。
シニア期になると、関節炎や椎間板ヘルニア、床ずれといった、痛みを伴う病気にかかりやすくなります。また、目に見えない内臓の病気や歯周病などが原因で、不快感を感じているのかもしれません。
特に夜間は、周囲が静かになるため、日中は気にならなかった痛みを強く感じやすい時間帯です。寝返りを打った時に関節が痛む、同じ体勢でいることで床ずれが痛むなど、特定のタイミングで「キャン」と鳴く場合は、体のどこかに痛みや不快感を抱えているサインと考えられます。愛犬の体を優しく触ってみて、嫌がる場所がないか確認することも大切です。
③生理的な要求:空腹、喉の渇き、トイレに行きたい
お腹が空いた、喉が渇いた、おしっこがしたい、といった単純な生理的要求が原因であることも考えられます。
若い頃は朝までぐっすり眠れていたとしても、加齢によって消化機能や代謝が変化し、夜中にお腹が空きやすくなることがあります。また、腎機能の低下により尿の量が増え、夜間にトイレに行きたくなることも少なくありません。
特に、寝る前の食事から時間が経ちすぎている場合や、いつでも水が飲める環境にない場合は注意が必要です。要求が満たされれば鳴き止むことが多いため、比較的気づきやすい原因と言えるでしょう。ただし、要求に応えすぎると夜泣きが習慣化する可能性もあるため、注意深い対応が求められます。
④不安やストレス:視力・聴力の低下や環境の変化が影響
目や耳が不自由になることで、強い不安を感じて夜泣きをしているケースです。
犬は周囲の状況を視覚や聴覚で把握しています。しかし、シニア期に入り白内障で視力が落ちたり、聴力が低下したりすると、暗く静かな夜間に孤立しやすくなります。飼い主の姿が見えない、物音が聞こえないといった状況が、大きな不安やストレスにつながるのです。
また、引っ越し、家族構成の変化、飼い主の長期不在といった環境の変化も、繊細な老犬にとっては大きなストレス要因となります。自分の置かれている状況が理解できず、助けを求めるように鳴き続けることがあります。飼い主の存在をそばに感じるだけで安心して鳴き止む場合は、この原因が考えられます。
⑤生活リズムの乱れ:昼間の活動不足で夜眠れない
昼間に十分な活動ができていないと、生活リズムが乱れて夜に眠れなくなります。
足腰が弱って散歩の時間が短くなったり、寝たきりに近くなったりすると、日中の消費エネルギーが減り、睡眠時間が増加します。その結果、夜になっても体力が有り余ってしまい、眠れずに退屈さから鳴いてしまうのです。
これは「昼夜逆転」とも呼ばれ、特に認知機能が低下している犬によく見られる傾向があります。日中に飼い主とのコミュニケーションや遊びといった刺激が少ないことも、生活リズムの乱れを助長します。夜間に元気に動き回ろうとしたり、遊びをせがむように鳴いたりする場合は、日中の活動不足を疑ってみましょう。
【原因別に解説】老犬の夜泣きへの具体的な対処法7選

原因が特定できたら、次はいよいよ具体的な対策の実践です。
ここでは、原因別に7つの具体的な対処法を詳しくご紹介します。複数の対策を組み合わせることで、より効果が期待できる場合もあります。愛犬の状態に合わせて、できることから試してみてください。
①認知症が疑われる場合:昼間の刺激で昼夜逆転を整える
認知症による夜泣きには、昼夜のメリハリをつける生活を意識させることが最も重要です。
脳に適度な刺激を与え、体内時計を正常な状態に近づけることを目指します。これにより、夜は眠り、昼は活動するというリズムを取り戻しやすくなります。
具体的には、午前中にカーテンを開けて太陽の光を浴びさせることが効果的です。カートに乗せて短い散歩に出かけ、外の匂いや音に触れさせるだけでも良い刺激になります。また、簡単な知育トイを使ったり、優しくマッサージをしたりと、五感を穏やかに刺激する時間を作りましょう。夜は部屋を暗くして静かな環境を整え、寝る時間であることを体に教えてあげることが大切です。
②痛みを和らげるケア:寝床の環境改善とマッサージ
身体的な痛みが原因の場合、愛犬が快適に休める環境を整えることが先決です。
特に寝床は一日の多くを過ごす場所なので、痛みや不快感を最小限に抑える工夫が求められます。体圧を分散できる高反発のマットや、老犬用の介護ベッドなどを活用しましょう。
寝床の素材や硬さを見直すだけで、痛みが和らぎ、夜泣きが軽減されるケースは少なくありません。また、血行を促進し、筋肉のこわばりを和らげる優しいマッサージも効果的です。ただし、痛がっている場所を無理に触るのは避け、獣医師に相談しながら適切なケアを行いましょう。痛みの根本原因が病気にある場合は、動物病院での治療が不可欠です。
③食事や飲水の工夫:寝る前の食事で空腹を防ぐ
空腹や喉の渇きによる夜泣きは、食事のタイミングや内容を工夫することで防げます。
夜中の空腹を防ぐためには、一日の食事量を3〜4回に分け、そのうちの一回を就寝の直前に与えるのが効果的です。このとき、消化の良いフードを選んだり、お湯でふやかしたりしてあげると、胃腸への負担を軽減できます。
また、いつでも新鮮な水が飲めるように、寝床の近くに水飲みボウルを設置してあげましょう。特に、自力で水飲み場まで移動するのが難しい犬の場合は、飼い主が気づいて飲ませてあげる配慮が必要です。ただし、夜間の飲水量が極端に多い場合は病気の可能性もあるため、注意深く観察してください。
④不安を取り除く工夫:飼い主の匂いで安心させる
視力や聴力の低下による不安には、飼い主の存在を感じさせて安心感を与えることが何よりの薬です。
愛犬が安心して眠れるように、飼い主の匂いがついた使い古しのTシャツやタオルを寝床に置いてあげましょう。慣れ親しんだ匂いに包まれることで、孤独感が和らぎ、リラックス効果が期待できます。
また、飼い主の寝室に愛犬のベッドを移動させ、同じ空間で眠るのも一つの方法です。夜中に鳴き始めたら、すぐに「大丈夫だよ」と優しく声をかけ、そっと体を撫でてあげてください。飼い主がそばにいることを認識させるだけで、犬の不安は大きく軽減されます。過剰な反応は避け、あくまで穏やかに接することがポイントです。
⑤生活リズムの改善:無理のない範囲で日光浴や散歩を
生活リズムの乱れによる夜泣きには、日中の活動量を意識的に増やすことが効果的です。
目的は、昼間に適度に疲れさせて、夜に自然な眠気を誘うことにあります。足腰が弱っていても、カートに乗せて外に連れ出し、日光浴をさせながら外の空気に触れさせるだけでも十分な活動になります。
室内でも、ボールを優しく転がしてあげたり、おやつを探させるノーズワークを取り入れたりするなど、軽い運動や遊びの時間を設けましょう。大切なのは、犬の体力に合わせて無理のない範囲で行うことです。日中に適度な刺激と運動を取り入れることで、夜間の睡眠の質が向上し、夜泣きの減少につながります。
⑥快適な睡眠環境の整備:温度・湿度と寝床の見直し
犬がぐっすり眠るためには、人間と同じように、快適な睡眠環境が不可欠です。
特に老犬は体温調節機能が低下しているため、室内の温度や湿度管理が重要になります。夏は涼しく、冬は暖かい、犬が快適だと感じる室温(一般的に20〜25℃程度)を保つように心がけましょう。エアコンの風が直接当たらない場所に寝床を設置することも大切です。
また、寝床自体が清潔で快適であることも重要なポイントです。トイレの失敗が増えている場合は、ペットシーツを敷いたり、洗いやすい素材のベッドを選んだりして、常に清潔な状態を保ちましょう。静かで落ち着ける場所に寝床を移すだけで、安心して眠れるようになることもあります。
⑦サプリメントや薬の活用:獣医師に相談の上で検討
様々な対策を試しても改善しない場合は、サプリメントや薬の力を借りるという選択肢もあります。
認知機能の維持をサポートする成分(DHA・EPAなど)が含まれたサプリメントや、不安を和らげる効果が期待できる鎮静系のサプリメントが市販されています。これらは夜泣きの緩和に役立つ可能性があります。
ただし、サプリメントはあくまで栄養補助食品であり、薬ではありません。また、夜泣きの原因が病気にある場合、より専門的な治療薬が必要になることもあります。自己判断で与えるのではなく、必ずかかりつけの獣医師に相談し、愛犬の状態に合ったものを処方してもらうようにしましょう。
その夜泣き、病気のサインかも?動物病院へ行くべき症状

夜泣きは単なる老化現象と片付けられないケースも多く存在します。
背後には、治療が必要な病気が隠れている可能性も否定できません。ここでは、どのような場合に動物病院を受診すべきか、その判断基準について解説します。
これが見られたら要注意!受診を判断する5つのポイント
夜泣きに加えて以下の症状が見られる場合は、迷わず動物病院を受診してください。
これらは、体が発している重要なSOSサインです。早期発見・早期治療が、愛犬の苦痛を和らげる鍵となります。
1. 食欲や元気がない:夜泣き以外に、普段と比べて食欲が落ちたり、ぐったりして動かなかったりする。
2. 体を痛がる素振り:抱き上げようとしたり、特定の部分を触ったりすると「キャン」と鳴いて嫌がる。
3. 呼吸の異常:呼吸が速い、苦しそう、咳き込むなどの症状がある。
4. トイレの変化:おしっこの量や回数が極端に増えたり減ったりする、血が混じる、排泄時に痛そうにする。
5. 急激な行動の変化:突然攻撃的になった、痙攣(けいれん)を起こした、同じ場所をぐるぐる回り続ける。
病院で伝えるべきこと|夜泣きの状況を記録しておこう
的確な診断のためには、飼い主からの正確な情報が非常に重要になります。
動物病院へ行く前には、夜泣きの様子をできるだけ詳しく記録し、メモを持参することをおすすめします。獣医師に状況が伝わりやすくなり、スムーズな診察につながります。
【記録しておくべきポイント】
* いつから始まったか(例:1ヶ月前から)
* どのような鳴き声か(例:クーンクーン、遠吠えのような声)
* どのくらいの頻度・時間か(例:毎晩、深夜2時頃から1時間ほど)
* どんな状況で鳴くか(例:部屋を暗くすると鳴き始める)
* 鳴いている時の他の様子(例:歩き回っている、震えている)
* 夜泣き以外の変化(例:食欲、排泄、歩き方など)
獣医師はどこを見ている?行われる検査の例
獣医師は、夜泣きの裏に隠れた病気を見つけるために、様々な角度から検査を行います。
飼い主からの問診を元に、まずは体を触って痛がる場所がないか、お腹にしこりがないかなどを確認する「触診」を行います。これにより、関節や内臓の異常について、ある程度のあたりをつけることができます。
さらに詳しく調べるために、血液検査や尿検査、レントゲン検査、超音波(エコー)検査などが行われることもあります。血液検査では内臓の機能や炎症の有無が分かり、レントゲンやエコー検査では骨や内臓の形に異常がないかを確認できます。これらの検査は、外からでは分からない病気を発見するために不可欠なものです。
飼い主ができること|追い詰められる前に行動しよう

愛犬の夜泣きは、飼い主自身の心と体にも大きな負担をかけます。
介護疲れで追いつめられてしまう前に、飼い主自身ができること、頼れる選択肢があることを知っておくことが大切です。
夜泣きを決して叱らないで
夜泣きに対して、大声で叱ったり、罰を与えたりすることは絶対にやめてください。
夜泣きは、犬が何らかの苦痛や不安を感じているサインです。それを叱ってしまうと、犬はさらに不安になり、問題行動が悪化する可能性があります。また、飼い主との信頼関係を損なうことにもつながりかねません。
つらい気持ちは分かりますが、まずは「どうしたの?」と優しく声をかけ、冷静に原因を探ることが大切です。叱っても夜泣きは解決しない、ということを心に留めておいてください。あなたの冷静な対応が、愛犬に安心感を与えます。
近所迷惑が心配な場合の防音対策
近隣への音が気になる場合は、できる範囲で防音対策を行い、精神的な負担を軽くしましょう。
完全に音を遮断することは難しいですが、対策を講じることで「できる限りのことはしている」という安心感が得られます。まずは、窓に厚手の遮光・防音カーテンを取り付けるのが手軽で効果的です。
また、壁際に犬の寝床がある場合は、壁から少し離すだけでも音の伝わり方が変わります。床に防音マットやカーペットを敷くことも、鳴き声の響きを和らげるのに役立ちます。もし可能であれば、日頃からご近所の方とコミュニケーションを取り、事情を説明しておくことも一つの方法です。
一人で抱え込まないで|家族や専門家を頼ろう
老犬の介護は、決して一人で抱え込むべきではありません。
毎晩続く夜泣きへの対応は、心身ともに疲弊します。まずは家族に協力を求め、夜間の対応を交代してもらうなど、自分の休息時間を確保することが非常に重要です。
また、かかりつけの獣医師やドッグトレーナーといった専門家に相談することも大切です。客観的なアドバイスをもらうことで、解決の糸口が見つかるかもしれません。介護に疲れ果ててしまう前に、周囲のサポートを積極的に活用しましょう。あなた自身が健やかでいることが、愛犬にとって一番の支えになります。
老犬の夜泣きに関するよくある質問
ここでは、老犬の夜泣きに関して多くの飼い主様から寄せられる質問にお答えします。
具体的な疑問を解消し、愛犬との生活に役立ててください。
Q1. 老犬の夜泣きは、いつまで続くものですか?
一概に「いつまで」とは言えませんが、原因への対処によって改善する可能性は十分にあります。
夜泣きの期間は、その原因によって大きく異なります。例えば、身体的な痛みが原因であれば、動物病院での治療によって痛みが和らげば、夜泣きはすぐに収まるかもしれません。生活リズムの乱れが原因であれば、日中の過ごし方を工夫することで数週間で改善が見られることもあります。
一方で、認知症が原因の場合は、病気の進行とともに症状が変化するため、長期的な付き合いになる可能性があります。しかし、適切なケアや投薬によって、夜泣きの頻度や程度をコントロールすることは可能です。諦めずに原因に合ったケアを続けることが大切です。
Q2. 夜泣き対策のサプリメントは本当に効果がありますか?
効果には個体差がありますが、症状緩和の一助となる可能性はあります。
夜泣き対策として販売されているサプリメントには、脳の健康をサポートするDHA・EPAや、精神を安定させる効果が期待されるテアニンなどが含まれていることが多いです。これらが愛犬の体質や症状に合えば、不安を和らげたり、認知機能の低下を緩やかにしたりする効果が期待できます。
ただし、サプリメントは医薬品ではないため、劇的な変化をもたらすものではありません。あくまで「日々のケアを補助するもの」と捉えましょう。メリットは副作用のリスクが低いことですが、デメリットとして効果を実感しにくい場合もあります。必ず獣医師に相談の上、使用を検討してください。
Q3. 夜泣きを無視するのは逆効果ですか?
原因によりますが、基本的には完全に無視するのは推奨されません。
特に、痛みや不快感、トイレの要求といった生理的な原因で鳴いている場合、無視することは愛犬の苦痛を長引かせるだけです。また、不安から鳴いている場合に無視を続けると、さらに不安を増大させ、飼い主への不信感につながる恐れがあります。
ただし、「鳴けば構ってもらえる」という学習からくる要求鳴きの場合は、毎回すぐに応じると行動が強化されてしまう可能性があります。見極めが難しいですが、まずは「どうしたの?」と様子を確認し、体のチェックやトイレへの誘導など、必要なケアをしてあげることが基本の対応となります。
Q4. 老犬ホームに預けるという選択肢はありですか?
はい、飼い主と愛犬双方にとって重要な選択肢の一つです。
老犬介護は24時間体制になりがちで、飼い主様の心身の限界や、家庭・仕事との両立が困難になる場合があります。「最後まで家で看るのが愛情」と自分を追い詰める必要はありません。専門のスタッフがいる老犬ホームに預けることで、愛犬は適切なケアを受けられ、飼い主様も自分の生活を取り戻すことができます。
メリットは、専門的な介護を受けられる安心感と、飼い主の負担軽減です。デメリットとしては、経済的な負担や、愛犬と離れる寂しさが挙げられます。しかし、飼い主が倒れてしまっては元も子もありません。老犬ホームは決して介護を放棄する場所ではなく、愛犬と飼い主が共に穏やかに過ごすための、前向きな選択肢だと考えてください。
まとめ:原因に合ったケアで穏やかな夜を。愛犬と飼い主のためにできること

老犬の夜泣きは、飼い主にとって非常につらい問題ですが、その裏には必ず原因が隠されています。
この記事で解説したように、夜泣きの原因は認知症や体の痛み、不安、生理的要求など様々です。まずは愛犬をよく観察し、「なぜ鳴いているのか」を突き止めることが、解決への最も重要な一歩となります。
原因がわかれば、対処法も見えてきます。昼間の過ごし方を工夫したり、寝床の環境を整えたり、食事の時間を調整したりと、できることはたくさんあります。時には動物病院で専門家の力を借りることも必要です。一人で抱え込まず、様々な対策を試しながら、愛犬とご自身の負担を軽くする方法を探していきましょう。この記事が、あなたと愛犬の穏やかな夜を取り戻す一助となれば幸いです。
大切なペットの移動にはペットタクシー「かるたく」がおすすめ

ペットタクシー「かるたく」は、愛玩動物飼養管理士の資格を持つドライバーが、大切なペットを安心・安全に送迎するサービスです。
動物病院への送迎が全体の55.9%を占め、ペットの体調に配慮した運転を心掛けています。料金は事前にシミュレーションでき、明瞭な価格設定が魅力です。車内は広々としており、多頭飼いの方も安心。
ペット用ラグジュアリークッションやスロープを完備し、快適な移動をサポートします。さらに、乗車毎の除菌・清掃・消臭を徹底し、清潔な環境を提供。
ペットホテル、引っ越し、トリミング、旅行など、さまざまなシーンでご利用いただけます。今なら最大50%オフのキャンペーン実施中。大切なペットとの移動に、ぜひ「かるたく」をご利用ください。