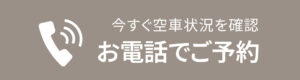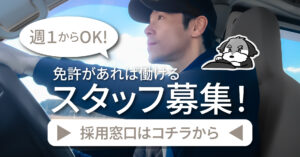愛犬の睡眠時間、長すぎたり短すぎたりして「これって普通なの?」と心配になった経験はありませんか。この記事では、犬の睡眠時間の平均を子犬・成犬・老犬といった年齢別、そして犬種ごとに詳しく解説します。
さらに、睡眠時間が変化する背景にある病気のサインやストレス、愛犬がぐっすり眠れる環境づくりのコツまで徹底的にご紹介します。この記事を読めば、あなたの愛犬の睡眠に関するあらゆる疑問が解消され、今日から実践できる健康管理のヒントが得られるでしょう。
まずは結論!犬の睡眠時間と年齢別の違いがわかる比較表

犬の睡眠時間は、年齢によって大きく異なります。まず結論として、愛犬の睡眠時間が正常かどうかを判断するための目安を、わかりやすい比較表にまとめました。
これからご紹介する内容はあくまで平均的な時間です。あなたの愛犬の様子と照らし合わせながら、健康状態をチェックする参考にしてください。
| 年齢 | 1日の平均睡眠時間 | 特徴 |
|---|---|---|
| 子犬(〜1歳) | 18〜20時間 | 体と脳が急速に成長するため、多くの睡眠を必要とします。寝たり起きたりを繰り返します。 |
| 成犬(1〜7歳頃) | 12〜15時間 | 活動と休息のバランスが取れる時期。飼い主の生活リズムに合わせて眠るようになります。 |
| 老犬(7歳頃〜) | 18時間以上 | 体力の低下から、再び睡眠時間が長くなる傾向があります。眠りが浅くなることも多いです。 |
この表はあくまで一般的な目安です。犬種や個体差によっても睡眠時間は変わるため、日頃から愛犬の様子をよく観察することが大切になります。
犬の睡眠時間が人間より長い2つの理由

犬の睡眠時間が人間(約6〜8時間)と比べて非常に長いのは、その睡眠の質と野生時代の習性に由来します。ただ寝ている時間が長いだけでなく、その中身が人間とは根本的に違うのです。ここでは、犬がロングスリーパーである2つの大きな理由を解説します。
①浅い眠りの「レム睡眠」がほとんどだから
犬の睡眠が長い最大の理由は、睡眠の大部分が「レム睡眠」という浅い眠りだからです。レム睡眠とは、脳は活発に動いている一方で、体は深くリラックスしている状態の眠りを指します。人間でいうと、夢を見ている時の眠りに近いです。
犬の睡眠の内訳は、レム睡眠が約80%、深い眠りの「ノンレム睡眠」が約20%といわれています。人間とはこの比率がほぼ真逆なのです。浅い眠りが多いため、少しの物音でもすぐに目を覚ますことができます。その分、熟睡できる時間が短いため、合計の睡眠時間で補っているのです。
②野生時代の名残で警戒しながら眠るから
もう一つの理由は、外敵から身を守っていた野生時代の習性が今も残っているためです。野生で暮らしていた頃、犬はいつ外敵に襲われるかわからない環境で生きていました。そのため、完全に無防備になる深い眠りは、命の危険に直結します。
この名残から、現代の犬も熟睡する時間は短く、「うたた寝」のような浅い眠りを繰り返すことで、合計の睡眠時間を確保しています。飼い主のそばで安心して寝ているように見えても、本能レベルで常に周囲を警戒しているのです。この習性こそ、犬が小さな物音にも敏感に反応して目を覚ます理由といえるでしょう。
【年齢別】犬の睡眠時間の目安と特徴
犬の健康状態を知るうえで、年齢に応じた睡眠時間を理解することは非常に重要です。人間が赤ちゃん、大人、お年寄りで必要な睡眠時間が違うように、犬もライフステージによって眠りのスタイルが大きく変化します。ここでは子犬、成犬、老犬(シニア犬)の3つのステージに分けて、それぞれの睡眠時間と特徴を詳しく見ていきましょう。
子犬の睡眠時間(生後〜1歳):1日18〜20時間
子犬期は、心身が爆発的に成長するための最も重要な時期であり、1日の大半を眠って過ごします。その睡眠時間は、平均して18時間から20時間にも及びます。これは「寝る子は育つ」という言葉通り、眠っている間に成長ホルモンが分泌され、骨格や筋肉、脳が発達するためです。
子犬はまだ体力がなく、起きている間は見るものすべてに興味津々で全力で活動するため、すぐにエネルギーを使い果たしてしまいます。そのため、短い時間遊んだかと思うと、次の瞬間にはコテッと眠ってしまうというサイクルを繰り返すのが普通です。心配になるかもしれませんが、これは健やかな成長のために不可欠な睡眠なので、無理に起こさず、そっと見守ってあげてください。
成犬の睡眠時間(1歳〜7歳頃):1日12〜15時間
1歳を過ぎた成犬になると、子犬期に比べて睡眠時間は落ち着き、1日12時間から15時間が平均となります。この時期は体力もつき、生活リズムが安定してくるのが特徴です。飼い主の生活サイクルに合わせ、飼い主が仕事などで不在の日中はのんびりと眠って過ごし、家族が帰宅する夕方から夜にかけて活動的になる子が多いでしょう。
成犬の睡眠は、浅い眠りを繰り返しながら合計時間を確保している点は子犬期と変わりません。しかし、安全な家庭環境で暮らすことに慣れると、よりリラックスして眠れるようになります。飼い主との信頼関係が深まるほど、安心して眠る時間も増えていく傾向にあります。
老犬(シニア犬)の睡眠時間(7歳頃〜):1日18時間以上
7歳頃から始まるシニア期に入ると、犬の睡眠時間は再び長くなり、1日に18時間以上眠ることも珍しくありません。これは体力の低下や、代謝機能の衰えが主な原因です。若い頃と同じように活動すると疲れやすくなるため、体を回復させるためにより多くの休息が必要になるのです。
また、老犬になると眠りが浅くなる傾向が強まります。聴覚や視覚が衰えることで不安を感じやすくなり、物音に敏感になって何度も目を覚ますこともあります。昼間に寝ている時間が増え、夜中に起きてしまう「昼夜逆転」のような行動が見られる場合は、認知機能の低下も考えられるため、注意深い観察が必要です。
【犬種・サイズ別】睡眠時間の目安

犬の睡眠時間は、年齢だけでなく、体の大きさや犬種によっても左右されます。一般的に、大型犬は小型犬よりも長く眠る傾向にあります。これは、大きな体を維持するために多くのエネルギーを消費し、その回復により多くの休息が必要になるためです.ここでは、犬のサイズ別に睡眠時間の目安をご紹介します。
小型犬(チワワ、トイ・プードルなど)の睡眠時間
チワワやトイ・プードルに代表される小型犬の平均睡眠時間は、成犬で12〜15時間ほどが目安です。小型犬は活発で遊び好きな犬種が多いですが、体が小さい分、疲れやすいという特徴も持っています。そのため、日中は短い睡眠をこまめに取ることで体力を回復させています。
また、小型犬は警戒心が強く、物音に敏感な子が多い傾向にあります。その性質から、常に周囲を警戒して浅い眠りをしている時間が長くなりがちです。飼い主のそばで安心して眠れる環境を整えてあげることで、睡眠の質を高めることができます。
中型犬(柴犬、ウェルシュ・コーギーなど)の睡眠時間
柴犬やコーギーなどの中型犬の睡眠時間は、小型犬と大型犬の中間にあたる12〜14時間程度が一般的です。中型犬は体力と活発さのバランスが取れている犬種が多く、飼い主との活動的な時間を楽しむ一方で、休息もしっかりとる傾向にあります。
もともと作業犬や牧畜犬として活躍していた犬種が多いため、日中の活動量が睡眠の質に大きく影響します。散歩や遊びの時間が充実していれば、夜はぐっすりと眠ってくれるでしょう。適度な運動を心がけることが、健康的な睡眠サイクルの維持につながります。
大型犬(ゴールデン・レトリバー、秋田犬など)の睡眠時間
ゴールデン・レトリバーなどの大型犬は、体を維持するために多くのエネルギーを必要とするため、睡眠時間が長くなる傾向にあり、1日14〜18時間眠ることもあります。その穏やかな見た目通り、のんびりと寝て過ごす時間を好む子が多いのが特徴です。
大型犬は成長期に体が急激に大きくなるため、特に子犬の頃は骨や関節への負担を考慮し、十分な睡眠時間を確保することが極めて重要です。成犬になってからも、激しい運動の後などは、体を回復させるためにいつもより長く眠ることがあります。愛犬の活動量に合わせて、ゆっくり休める時間を確保してあげましょう。
【要注意】睡眠時間の変化でわかる病気やストレスのサイン

犬の睡眠時間は、健康状態を映し出すバロメーターです。いつもより極端に長い、あるいは短いといった変化が見られる場合、それは体調不良やストレスのサインかもしれません。単なる「寝すぎ」や「寝不足」と軽く考えず、背後に隠れた病気の可能性にも目を向けることが、愛犬の健康を守る上で非常に重要です。
睡眠時間が「長すぎる」場合に考えられる原因と病気
いつもより明らかに睡眠時間が長い状態が続く場合、何らかの病気や心の問題が隠れている可能性があります。特に、元気や食欲も同時にない場合は注意が必要です。
考えられる原因には、甲状腺機能低下症や心臓病、関節炎などの痛み、分離不安や退屈によるストレスなどが挙げられます。これらの病気や問題は、動物病院での診察や飼育環境の見直しによって改善が期待できます。普段と違うと感じたら、早めに専門家へ相談しましょう。
睡眠時間が「短すぎる」場合に考えられる原因と病気
逆に、睡眠時間が極端に短くなったり、夜中に何度も起きたりする場合も、心身の不調が考えられます。特にシニア犬の場合は、注意深く観察する必要があります。
睡眠時間が短くなる原因としては、認知症(昼夜逆転)、痛みやかゆみを伴う皮膚病、脳の病気(てんかんなど)が考えられます。これらの症状は、犬にとって大きな苦痛を伴います。睡眠が短いだけでなく、落ち着きがない、体を頻繁にかくなどの行動が見られたら、病気の可能性を疑い、獣医師の診察を受けることを強く推奨します。
今日からできる!愛犬がぐっすり眠れる快適な環境づくりの5つのコツ

愛犬の健康にとって、睡眠の「量」だけでなく「質」も非常に大切です。飼い主が少し工夫するだけで、愛犬はもっと安心して深く眠れるようになります。ここでは、今日からすぐに実践できる、愛犬の快適な睡眠環境を整えるための5つの具体的なコツをご紹介します。これらのポイントを実践し、最高の寝床をプレゼントしてあげましょう。
①安心できる静かな場所に専用のベッドを用意する
犬が安心して眠るためには、自分だけの安全なテリトリーとなる「専用の寝床」を用意してあげることが最も重要です。人の出入りが激しい場所や、テレビなどの音が直接聞こえる場所は避け、部屋の隅などの静かで落ち着ける場所を選びましょう。
屋根付きのクレートやハウスは、犬が本能的に好む「巣穴」のような環境を作れるため特におすすめです。体にフィットするフカフカのベッドや、季節に合わせた素材のマットを敷いてあげることで、より快適性が増します。自分だけの場所だと認識させ、そこで過ごす時間が心地よいものだと教えてあげることが大切です。
②室温や湿度を快適に保つ
犬は人間よりも体温調節が苦手なため、寝床の温度と湿度を快適に保つことが、質の高い睡眠に直結します。犬にとっての快適な室温は20℃〜25℃程度、湿度は40%〜60%が目安とされています。
夏場はエアコンやクールマットを活用して熱中症を防ぎ、冬場はペット用のヒーターや暖かい毛布で寒さ対策をしましょう。特に、子犬や老犬、体温調節が苦手な短頭種などは、飼い主がより一層気をつけて管理してあげる必要があります。犬が自分で体温を調整できるよう、暖かい場所と涼しい場所を両方用意しておくのも良い工夫です。
③日中に適度な運動をさせてエネルギーを発散させる
日中に適度な運動をさせて心身ともに満たしてあげることは、夜の安眠に欠かせません。毎日の散歩はもちろん、室内でのボール遊びや知育トイなどを活用して、愛犬のエネルギーをしっかりと発散させてあげましょう。
運動不足はストレスの原因となり、問題行動や夜泣きにつながることがあります。一方で、過度な運動は、特に子犬や老犬の関節に負担をかけるため禁物です。愛犬の年齢や体力に合った、適切な量の運動を心がけることが重要です。心地よい疲労感が、自然と深い眠りへと誘ってくれるでしょう。
④寝る前の食事や遊びは避ける
人間と同じように、犬も寝る直前の食事や激しい遊びは、睡眠の質を低下させる原因となります。就寝前に食事をすると、睡眠中も消化器官が活発に働き続けるため、体が完全に休まりません。食事は、寝る時間の2〜3時間前までには済ませておくのが理想的です。
また、寝る前にボール投げなどの興奮する遊びをすると、交感神経が優位になってしまい、なかなか寝付けなくなってしまいます。夜はゆったりとした音楽を聴かせたり、優しくマッサージをしてあげたりするなど、リラックスできる時間を作ることを心がけましょう。穏やかな気持ちで眠りにつけるように導いてあげることが大切です。
⑤飼い主が生活リズムを整える
犬は飼い主の生活リズムに影響を受けやすいため、飼い主自身が規則正しい生活を送ることが、間接的に愛犬の安眠につながります。毎日決まった時間に起き、決まった時間に食事や散歩に行くことで、犬の体内時計も整いやすくなります。
特に、飼い主の就寝時間や起床時間がバラバラだと、犬もいつ休んでいいのかわからず、落ち着きなくなってしまいます。犬は家族の行動パターンをよく観察している賢い動物です。飼い主がリラックスして過ごす時間を作ることで、犬も「今は休む時間なんだ」と学習し、安心して眠りにつくことができるようになります。
寝相やいびきでわかる!犬の睡眠中の気持ちと健康サイン

犬が眠っている時の姿は、見ているだけで癒やされますが、実はその寝相やいびきには、犬の気持ちや健康状態を知るためのヒントが隠されています。ただ「可愛い」で終わらせず、愛犬が発するサインを読み解くことで、より深いコミュニケーションや健康管理につなげることができます。ここでは、寝ている姿からわかる犬の気持ちと注意点を見ていきましょう。
リラックス度MAX?寝相でわかる犬の気持ち
犬の寝相は、その時の心理状態やリラックス度を素直に表しています。例えば、体を丸めて眠るのは、体温を保ち、急所であるお腹を守るための本能的な寝方で、少し警戒しているサインかもしれません。
一方で、横向きにごろんと寝ていたり、仰向けになってお腹を見せる「へそ天」で寝ていたりする場合は、現在の環境に非常に安心し、リラックスしている証拠です。特にへそ天は、最も無防備な姿であり、飼い主やその場所を心から信頼していることを示しています。愛犬の寝相を観察すれば、今の暮らしに満足してくれているかどうかがわかるかもしれません。
そのいびき大丈夫?注意すべきいびきの特徴
犬も人間と同じようにいびきをかきますが、中には病気のサインが隠れている危険ないびきもあるため注意が必要です。普段はかかないのに急にいびきをかくようになった、いびきの音が大きくなった、苦しそうな呼吸が混じるなどの変化が見られた場合は、獣医師に相談しましょう。
特に、鼻から気管にかけての気道が短い「短頭種」は、構造的にいびきをかきやすい犬種です。しかし、それが当たり前だと思わず、呼吸が止まるような様子がないかは日頃からチェックする必要があります。
特に注意が必要な犬種(フレンチ・ブルドッグなどの短頭種)
フレンチ・ブルドッグやパグ、シーズーなどの「短頭種」は、その可愛らしい潰れた鼻が特徴ですが、解剖学的に気道が狭くなりがちです。このため、「短頭種気道症候群」という呼吸器系のトラブルを起こしやすく、いびきはその代表的な症状の一つです。
太り気味になると症状が悪化しやすいため、体重管理は非常に重要です。いびきだけでなく、普段からガーガー、ゼーゼーといった呼吸音が聞こえる場合は、一度動物病院で詳しく診てもらうことをお勧めします。
睡眠時無呼吸症候群の可能性
いびきの途中で呼吸が数十秒止まり、その後あえぐように呼吸を再開する様子が見られる場合、「睡眠時無呼吸症候群」の可能性があります。これは睡眠中に気道が塞がってしまうことで起こり、体に十分な酸素を取り込めなくなる危険な状態です。
この状態が続くと、心臓に大きな負担がかかるなど、様々な健康問題を引き起こすリスクがあります。肥満や、前述の短頭種気道症候群、喉や鼻の腫瘍などが原因で起こることがあります。愛犬の睡眠中にこのような症状が見られたら、放置せずに必ず獣医師の診察を受けてください。
犬の睡眠に関するよくある質問
ここでは、飼い主さんから特によく寄せられる犬の睡眠に関する疑問について、Q&A形式でお答えします。愛犬との暮らしの中で「これってどうなの?」と感じる細かな疑問を解消し、より良い関係づくりに役立ててください。
Q. 愛犬と一緒に寝てもいいですか?
A. 愛犬と一緒に寝ることには、メリットとデメリットの両方があるため、一概に良い・悪いとは言えません。メリットは、飼い主も犬も安心感を得られ、愛情や絆が深まる点です。
一方で、デメリットとしては、しつけの観点から主従関係が曖昧になる可能性や、ノミ・ダニなどの人獣共通感染症のリスクが挙げられます。また、飼い主の寝返りで犬を圧迫してしまう危険性もゼロではありません。これらの両面を理解した上で、それぞれの家庭に合ったスタイルを選択することが大切です。一緒に寝る場合は、衛生管理を徹底し、犬が自由に降りられる環境を確保しましょう。
Q. 夢を見てうなされたり、寝言を言ったりするのはなぜですか?
A. 犬も人間と同じように、眠っている間に夢を見ていると考えられています。寝ながら足をバタつかせたり、「クーン」と鳴いたりするのは、夢の中で走ったり、誰かとコミュニケーションを取ったりしているのかもしれません。
これは主に、脳が活発に動いている浅い眠り「レム睡眠」の時に見られる現象です。苦しそうに見えて心配になるかもしれませんが、これは正常な生理現象なので、無理に起こす必要はありません。優しく名前を呼んで、安心させてあげる程度に留めましょう。あまりに激しい場合は、てんかんなど他の病気の可能性も考えられるため、動画に撮って獣医師に相談すると良いでしょう。
Q. 夜中に何度も起きたり、夜鳴きをしたりするのはどうしてですか?
A. 夜中に何度も起きる、あるいは夜鳴きをする原因は、年齢や状況によって様々です。子犬の場合は、お腹が空いたり、トイレに行きたかったり、寂しかったりするのが主な理由です。ある程度の要求は無視して「夜は静かに寝る時間」だと教えるしつけも必要になります。
成犬の場合は、ストレスや運動不足、体のどこかの痛みなどが原因かもしれません。老犬の場合は、認知症による昼夜逆転や、不安感から夜鳴きをすることが増えます。いずれの場合も、原因を特定することが解決の第一歩です。まずは快適な睡眠環境が整っているかを見直し、それでも改善しない場合は、病気の可能性も視野に入れて獣医師に相談しましょう。
Q. 留守番中はほとんど寝ているようですが、問題ありませんか?
A. 留守番中に愛犬がほとんど寝て過ごしているのは、多くの場合、全く問題ありません。犬は元々、何もない時間は体力を温存するために眠る習性がある動物です。飼い主がいない時間は「休息の時間」と割り切り、リラックスして過ごせている証拠ともいえます。
ただし、注意すべき点もあります。帰宅した際に、過度に興奮する、破壊行動の痕跡がある、食欲がない、元気がないといった他のサインが見られる場合は、「分離不安」によるストレスから寝て過ごしている可能性も考えられます。愛犬が留守番中にリラックスできているか、帰宅後の様子もあわせて観察してあげることが大切です。
まとめ:毎日の睡眠チェックは最高の愛情表現!変化を見逃さず健康寿命を延ばそう

この記事では、犬の年齢別・犬種別の平均睡眠時間から、睡眠トラブルに隠された病気のサイン、そして快適な睡眠環境の作り方まで、幅広く解説してきました。
犬の睡眠時間は、彼らが言葉で伝えられない健康状態を教えてくれる、非常に重要なバロメーターです。「いつもより長いな」「最近よく起きるな」といった小さな変化に気づいてあげることが、病気の早期発見やストレスの軽減につながります。
愛犬が毎日安心してぐっすり眠れているか、その寝顔や寝息をチェックすることは、飼い主だからこそできる最高の愛情表現の一つです。この記事で得た知識を活かし、日々の観察を習慣にすることで、愛犬のかけがえのない健康と幸せな時間を、一日でも長く守ってあげましょう。もし少しでも不安な変化があれば、ためらわずに獣医師に相談してください。
大切なペットの移動にはペットタクシー「かるたく」がおすすめ

ペットタクシー「かるたく」は、愛玩動物飼養管理士の資格を持つドライバーが、大切なペットを安心・安全に送迎するサービスです。
動物病院への送迎が全体の55.9%を占め、ペットの体調に配慮した運転を心掛けています。料金は事前にシミュレーションでき、明瞭な価格設定が魅力です。車内は広々としており、多頭飼いの方も安心。
ペット用ラグジュアリークッションやスロープを完備し、快適な移動をサポートします。さらに、乗車毎の除菌・清掃・消臭を徹底し、清潔な環境を提供。
ペットホテル、引っ越し、トリミング、旅行など、さまざまなシーンでご利用いただけます。今なら最大50%オフのキャンペーン実施中。大切なペットとの移動に、ぜひ「かるたく」をご利用ください。